平成25年 愛知県人口動向調査結果(名古屋市分)
このページ内にある本文、参考図、表、PDF、Excelデータについて
このページ内にある本文、参考図、表、PDF、Excelデータは、オープンデータとして提供しており、クレジット表記すること(データ名:統計なごやweb版)により、二次利用していただくことが可能です。ご利用の場合は以下のページもご覧ください。
-
名古屋市におけるオープンデータの取り組み
オープンデータの概要及びご利用案内など
概要
このページは「平成25年愛知県人口動向調査」の名古屋市分について取りまとめたものです。この調査は、直近の国勢調査の結果をベースに、住民基本台帳及び外国人登録における毎月の出生、死亡、転入、転出などの異動数を加減することにより、人口及び世帯数の推計を行っているもので、今回は平成24年10月から平成25年9月までの1年間の異動状況を中心に取りまとめています。
外国人登録法の廃止と住民基本台帳法の改正について
平成24年7月9日に、外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の一部が改正されました。この法改正に伴い、世帯数と外国人人口の取扱を変更したため、人口の集計方法に変更が生じた。平成23年10月から平成24年9月の異動状況において、14,377世帯の世帯減及び2,619人の人口減(「その他減」として集計)が生じたことに注意してください。
1 人口
人口及び人口の対前年増減率の推移(各年10月1日現在)
平成25年10月1日現在の本市の人口は、前年より4,529人増の2,271,380人で、平成9年以降17年連続で増加し、過去最高となった。
参考図1
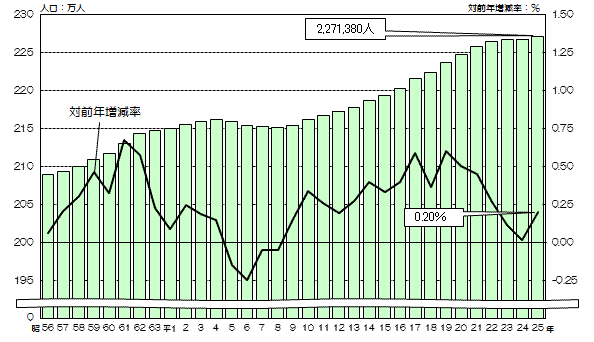
(注)平成24年は法改正に伴う外国人人口の取扱変更による数値変動を含む。
自然増減数、社会増減数及び人口増減数の推移(自然増減数、社会増減数:各年前年10月から当該年9月)(人口増減数:当該年10月1日現在の人口-前年10月1日現在の人口)
前年10月中から当該年9月中の1年間の、自然増減は201人の自然減、社会増減は4,730人の社会増となった。当該年10月1日現在の本市の人口から前年10月1日現在の本市の人口を引いた人口増減は、4,529人の人口増となった。
参考図2
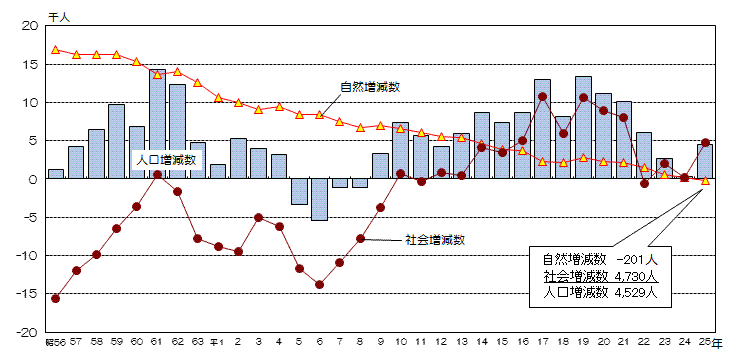
(注)社会増減数には、市内区間移動、その他の増減(転出取消、職権記載等、職権消除等、平成24年の法改正に伴う外国人人口の取扱変更による数値変動)を含む。
2 世帯数
- 平成25年10月1日現在の本市の世帯数は、1,034,154世帯(前年比10,726世帯増)となった。
- 1世帯当たり人員は2.20人(前年比0.01人減)となった。
3 自然動態
出生数、死亡数及び自然増減数の推移(各年前年10月から当該年9月)
平成25年(平成24年10月から平成25年9月までの1年間。以下同様。)の、出生数は20,229人(前年比245人増)、死亡数は、20,430人(前年比603人増)であった。この結果、自然増減数(出生数-死亡数)は201人の自然減(前年比358人減)となり、人口動向調査を開始して以来、はじめて自然減となった。
参考図3
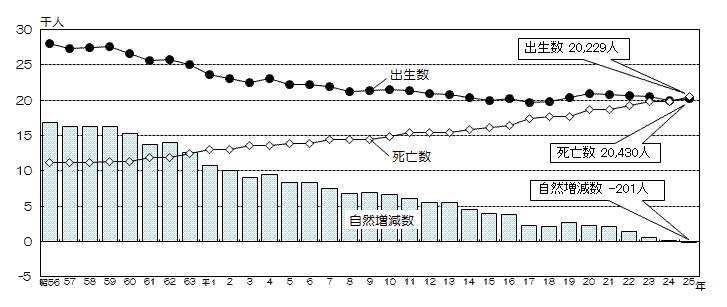
4 社会動態
転入数、転出数及び社会増減数の推移(各年前年10月から当該年9月)
平成25年の、転入数は151,212人(前年比3,143人増)、転出数は146,482人(前年比1,410人減)となった。社会増減数(転入数-転出数)は4,730人の社会増(前年比4,553人増)となった。
参考図4
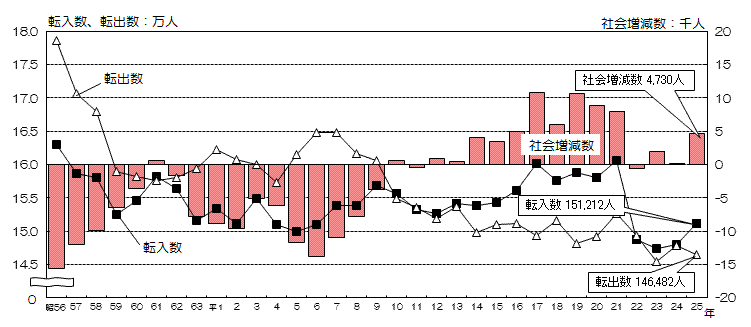
(注)市外との移動のほか、市内区間移動、その他の増減(転出取消、職権記載等、職権消除等)、平成24年の法改正に伴う外国人人口の取扱変更による数値変動)を含む。
地域別本市への転入数及び本市からの転出数(各年前年10月から当該年9月)
北海道・東北、関東、中部(愛知県を除く)、愛知県内他市町村、近畿、中国・四国、九州、国外、の8つの地域に分けて地域別に移動を集計した場合、平成25年の地域別の移動は、転入数、転出数とも愛知県内他市町村が最も多くなった。
参考図5
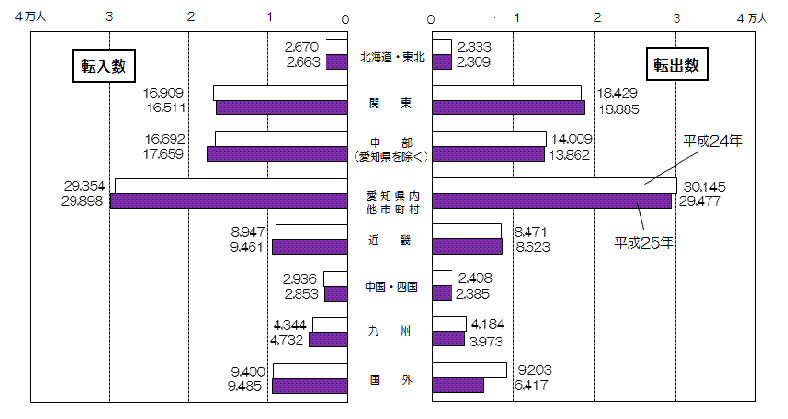
(注)国外への転出のうち外国人については、法改正前は出国した外国人の数を集計していたが、法改正後は、国外転出の届出をした外国人の数のみを集計しており、国外転出の届出をせずに出国した外国人は含まない。
地域別本市との社会増減数の推移(各年前年10月から当該年9月)
北海道・東北、関東、中部(愛知県を除く)、愛知県内他市町村、近畿、中国・四国、九州、国外、の8つの地域に分けて地域別に移動を集計した。平成25年の地域別の社会増減数は、社会増(転入超過)となった地域は、中部(愛知県を除く)の3,797人が最も多くなり、社会減(転出超過)となった地域は、関東の2,374人のみとなった。
参考図6
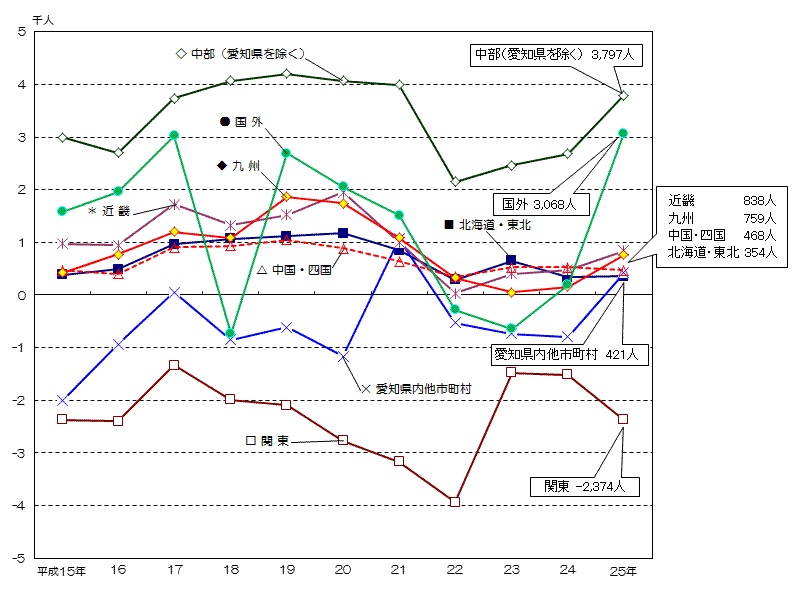
(注)平成24年7月の法改正により、外国人の国外転出の集計方法に変更が生じたため、平成23年以前と平成24年以降で、国外に対する社会増減数に連続性がない。
愛知県内他市町村との転入数、転出数及び社会増減数(各年前年10月から当該年9月)
平成25年の愛知県内他市町村との社会増減数では、社会増(転入超過)となった市町村は、豊田市の450人が最も多く、次いで刈谷市の234人、豊橋市の215人の順となった。社会減(転出超過)となった市町村は、長久手市の276人が最も多く、次いで北名古屋市の205人、尾張旭市の173人の順となった。
表1
| 前従地 | 平成25年 転入数 |
平成25年 転出数 |
平成25年 社会増減数 |
平成24年 転入数 |
平成24年 転出数 |
平成24年 社会増減数 |
対前年比 平成25年-平成24年 転入数 |
対前年比 平成25年-平成24年 転出数 |
対前年比 平成25年-平成24年 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 1,743 | 1,293 | 450 | 1,657 | 1,314 | 343 | 86 | -21 | 107 |
| 刈谷市 | 961 | 727 | 234 | 1,000 | 803 | 197 | -39 | -76 | 37 |
| 豊橋市 | 980 | 765 | 215 | 1,047 | 770 | 277 | -67 | -5 | -62 |
| 岡崎市 | 1,396 | 1,214 | 182 | 1,378 | 1,221 | 157 | 18 | -7 | 25 |
| 瀬戸市 | 953 | 810 | 143 | 880 | 888 | -8 | 73 | -78 | 151 |
| 安城市 | 773 | 650 | 123 | 712 | 656 | 56 | 61 | -6 | 67 |
| 知立市 | 415 | 303 | 112 | 471 | 367 | 104 | -56 | -64 | 8 |
| みよし市 | 437 | 349 | 88 | 453 | 374 | 79 | -16 | -25 | 9 |
| 半田市 | 524 | 451 | 73 | 534 | 514 | 20 | -10 | -63 | 53 |
| 知多市 | 530 | 461 | 69 | 526 | 503 | 23 | 4 | -42 | 46 |
表2
| 転出地 | 平成25年 転入数 |
平成25年 転出数 |
平成25年 社会増減数 |
平成24年 転入数 |
平成24年 転出数 |
平成24年 社会増減数 |
対前年比 平成25年-平成24年 転入数 |
対前年比 平成25年-平成24年 転出数 |
対前年比 平成25年-平成24年 社会増減数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長久手市 | 784 | 1,060 | -276 | 703 | 1,193 | -490 | 81 | -133 | 214 |
| 北名古屋市 | 842 | 1,047 | -205 | 838 | 1,253 | -415 | 4 | -206 | 210 |
| 尾張旭市 | 969 | 1,142 | -173 | 1,011 | 1,204 | -193 | -42 | -62 | 20 |
| 大府市 | 744 | 880 | -136 | 766 | 915 | -149 | -22 | -35 | 13 |
| 東海市 | 1,041 | 1,169 | -128 | 1,018 | 1,122 | -104 | 23 | 47 | -24 |
| 日進市 | 1,294 | 1,420 | -126 | 1,165 | 1,526 | -361 | 129 | -106 | 235 |
| 稲沢市 | 691 | 813 | -122 | 656 | 722 | -66 | 35 | 91 | -56 |
| 大治町 | 522 | 641 | -119 | 518 | 691 | -173 | 4 | -50 | 54 |
| 常滑市 | 252 | 351 | -99 | 299 | 306 | -7 | -47 | 45 | -92 |
| あま市 | 806 | 901 | -95 | 779 | 866 | -87 | 27 | 35 | -8 |
(注)平成24年1月4日に愛知郡長久手町が長久手市になった。表中の平成24年の長久手市の値は、平成23年10月から平成23年12月の長久手町の異動数を含む。
愛知県内他市町村との転入数、転出数、社会増減数の推移(各年前年10月から当該年9月)
愛知県内他市町村との移動について、昭和56年以降の社会増減数(転入数-転出数)の推移をみると、本市からの転出数の推移を色濃く反映したものとなっており、本市からの転出数が最大となった平成6年には社会減(本市からの転出超過)も最大となったが、次第に本市からの転出数が減少するとともに、本市への転入数も増加してきたため、平成17年には初めて社会増(本市への転入超過)となった。また、平成21年には転入数の大幅増加と転出数の減少により、4年ぶりに社会増となった。しかし、平成22年以降は再び社会減に転じ、3年連続で社会減となった。平成25年は転入数が前年より増加し、転出数が前年より減少し、4年ぶりに社会増に転じた。
参考図7
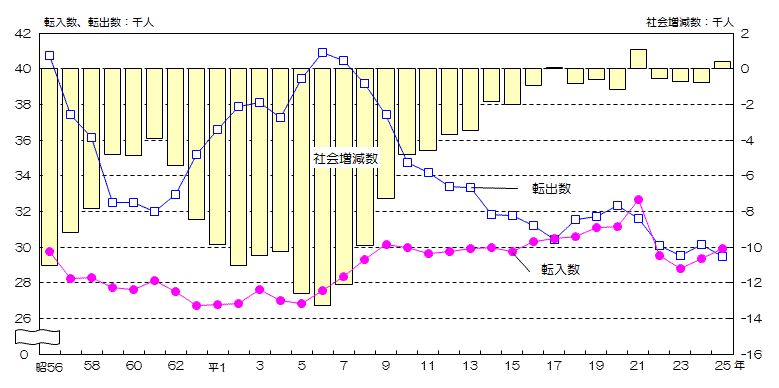
5 区別動向
区別人口(降順)(平成25年10月1日)
- 平成25年10月1日現在の区別人口が最も多いのは、緑区の235,631人で、平成16年から10年連続で最も多くなった。
- 平成25年10月1日現在の区別人口が最も少ないのは、熱田区の64,824人であった。
- 人口動向調査開始以来、過去最高の人口になったのは、東区、中区、守山区、緑区、名東区の5区となった。
参考図8
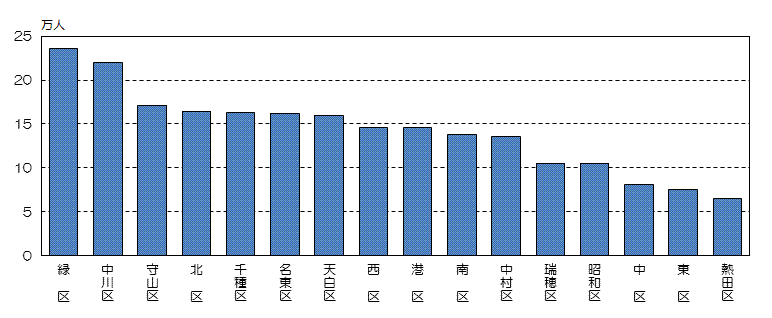
区別人口増減数(降順)(平成24年10月から25年9月)
平成25年の区別人口増減数では、平成24年と比べて昭和区が人口増となり、瑞穂区と熱田区が人口減となり、人口増は中区はじめ9区、人口減は南区はじめ7区となった。
参考図9
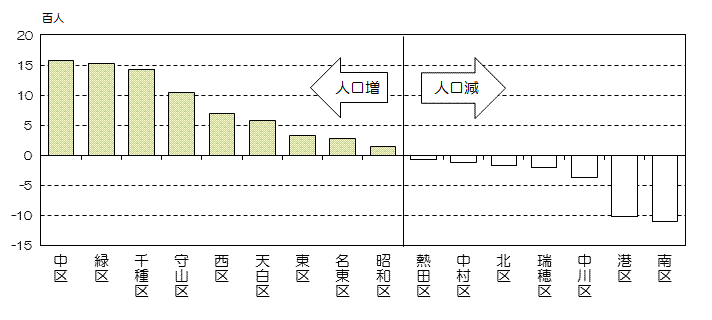
区別自然増減数(降順)(平成24年10月から25年9月)
平成25年の区別自然増減数では、自然増は緑区はじめ8区、自然減は中村区はじめ8区となった。
参考図10
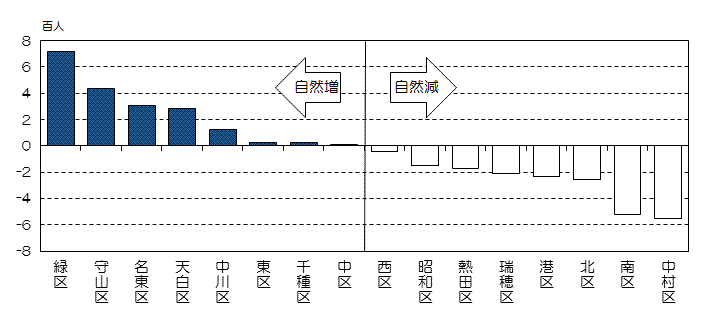
区別社会増減数(降順)(平成24年10月から25年9月)
平成25年の区別社会増減数では、平成24年と比べて北区と昭和区と天白区が社会増となり、社会増は中区はじめ12区、社会減は港区はじめ4区となった。
参考図11
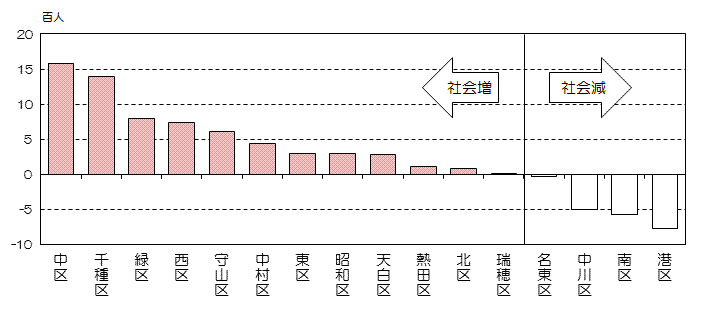
(注)社会増減数には、市内区間移動、その他の増減(転出取消、職権記載等、職権消除等)を含む。
区別、自然増減数、社会増減数(平成24年10月から平成25年9月)
参考図12
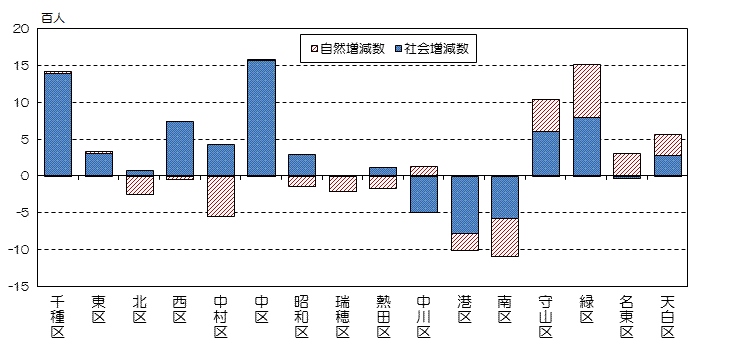
表3
| 区名 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 | 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | 守山区 | 緑区 | 名東区 | 天白区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口増減数 | 1,420 | 327 | -175 | 694 | -119 | 1,579 | 146 | -208 | -66 | -374 | -1,014 | -1,097 | 1,043 | 1,520 | 282 | 571 |
| 自然増減数 | 23 | 25 | -254 | -41 | -554 | 4 | -146 | -209 | -175 | 124 | -234 | -520 | 439 | 721 | 310 | 286 |
| 社会増減数 | 1,397 | 302 | 79 | 735 | 435 | 1,575 | 292 | 1 | 109 | -498 | -780 | -577 | 604 | 799 | -28 | 285 |
(注)社会増減数には、市内区間移動、その他の増減(転出取消、職権記載等、職権消除等)を含む。
区別、移動地域別社会増減数(平成24年10月から平成25年9月)
参考図13
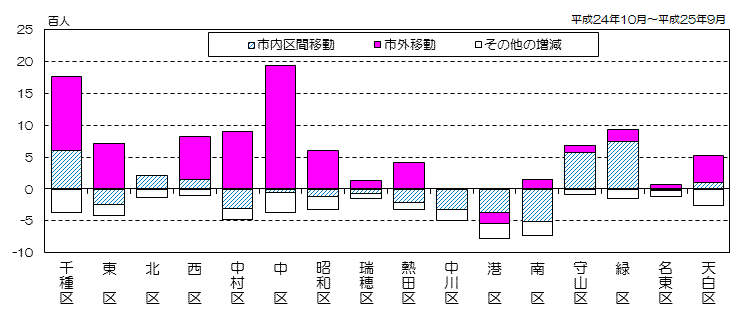
表4
| 区名 | 千種区 | 東区 | 北区 | 西区 | 中村区 | 中区 | 昭和区 | 瑞穂区 | 熱田区 | 中川区 | 港区 | 南区 | 守山区 | 緑区 | 名東区 | 天白区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 1,397 | 302 | 79 | 735 | 435 | 1,575 | 292 | 1 | 109 | -498 | -780 | -577 | 604 | 799 | -28 | 285 |
| 市内区間移動 | 613 | -242 | 211 | 149 | -303 | -59 | -112 | -66 | -206 | -315 | -360 | -505 | 574 | 753 | -25 | 112 |
| 市外移動 | 1,153 | 717 | -10 | 682 | 906 | 1,939 | 608 | 145 | 426 | 0 | -185 | 156 | 106 | 188 | 80 | 423 |
| その他の増減 | -369 | -173 | -122 | -96 | -168 | -305 | -204 | -78 | -111 | -183 | -235 | -228 | -76 | -142 | -83 | -250 |
6 年齢構成
区別年齢3区分別人口比率(各年10月1日現在)
- 平成25年10月1日現在の全市の年齢3区分別人口比率では、年少人口比率(14歳以下)は12.8%(昨年より0.1ポイント低下、10年前より0.9ポイント低下)、生産年齢人口比率(15から64歳)は64.2%(昨年より0.8ポイント低下、10年前より4.6ポイント低下)、老年人口比率(65歳以上)は22.9%(昨年より0.8ポイント上昇、10年前より5.4ポイント上昇)となった。
- 区別年少人口比率では、最も高いのは緑区の16.2%(昨年より0.1ポイント低下)、最も低いのは中区の7.6%(昨年より0.1ポイント上昇)となった、
- 区別生産年齢人口比率では、最も高いのは中区の70.8%(昨年より0.5ポイント低下)、最も低いのは南区の61.6%(昨年より0.9ポイント低下)となった。
- 区別老年人口比率では、最も高いのは南区の27.2%(昨年より1.1ポイント上昇)、最も低いのは名東区の19.5%(昨年より0.9ポイント上昇)となった。
参考図14
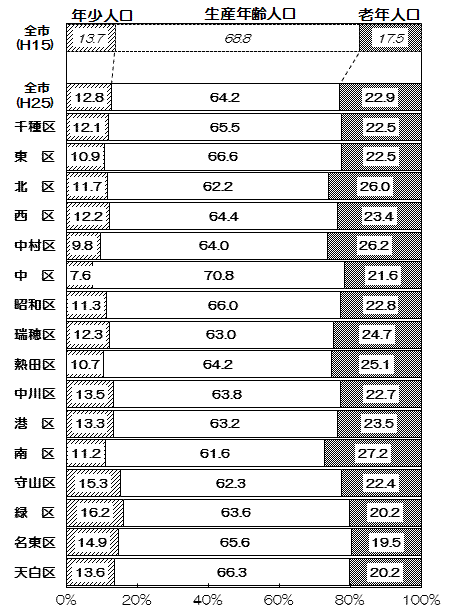
(注)年齢不詳を含まない人口総数を分母とする。
本市の年齢構成指数の推移(各年10月1日現在)
- 全市の年少人口指数は、ほぼ横ばいの20.0(昨年より0.1ポイント上昇)となった。
- 全市の老年人口指数は、年々上昇しており35.7(昨年より1.7ポイント上昇)となった。
- 全市の老年化指数は、大きく上昇しており179.0(昨年より7.6ポイント上昇)となった。
- 全市の従属人口指数は、年々上昇しており55.7(昨年より1.8ポイント上昇)となった。
参考図15
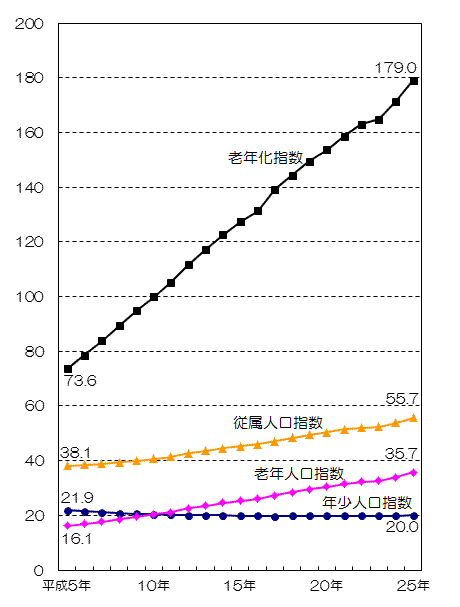
(注)年少人口指数=年少人口/生産年齢人口×100
老年人口指数=老年人口/生産年齢人口×100
従属人口指数=年少人口指数+老年人口指数
老年化指数=老年人口/年少人口×100
オープンデータ
平成25年 愛知県人口動向調査結果(名古屋市分)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
統計表(人口・世帯数)
統計表(年齢別人口)
統計表(自然動態)
統計表(社会動態)

この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
-
第12表 市町村、男女別県内(市外)からの転入数 (Excel 77.5 KB)

-
第13表 市町村、男女別県内(市外)への転出数 (Excel 76.5 KB)

-
第14表 市町村、男女別県内(市外)との社会増減数 (Excel 75.5 KB)

-
第15表 都道府県、男女別市外からの転入数 (Excel 51.0 KB)

-
第16表 都道府県、男女別市外への転出数 (Excel 51.0 KB)

-
第17表 都道府県、男女別市外との社会増減数 (Excel 50.0 KB)

-
第18表 市外との転入数、転出数、社会増減数等の推移 (Excel 39.0 KB)

-
第19表 年齢(11区分)、市町村別県内(市外)からの転入数 (Excel 44.0 KB)

-
第20表 年齢(11区分)、市町村別県内(市外)への転出数 (Excel 44.5 KB)

-
第21表 年齢(11区分)、市町村別県内(市外)との社会増減数 (Excel 44.5 KB)

-
第22表 年齢(5区分)、都道府県別市外との転入数、転出数、社会増減数 (Excel 46.5 KB)

-
第23表 年齢(5歳階級)別転入数、転出数、社会増減数の推移 (Excel 41.5 KB)


この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
-
第24表 区別、年齢(5歳階級)別転入数、転出数、社会増減数 (Excel 50.0 KB)

-
第25表 年齢(5歳階級)、男女別市外との転入数、転出数、社会増減数 (Excel 48.5 KB)

-
第26表 区別 、都道府県別市外からの転入数 (Excel 46.0 KB)

-
第27表 区別 、都道府県別市外への転出数 (Excel 45.5 KB)

-
第28表 区別 、都道府県別市外との社会増減数 (Excel 46.0 KB)

-
第29表 区別 、市町村別県内(市外)からの転入数 (Excel 49.5 KB)

-
第30表 区別 、市町村別県内(市外)への転出数 (Excel 50.0 KB)

-
第31表 区別 、市町村別県内(市外)との社会増減数 (Excel 50.0 KB)

-
第32表 区別 、前住地・転出地別、他区との転入数、転出数、社会増減数 (Excel 45.0 KB)

名古屋市オープンデータカタログサイトへのリンクです。名古屋市オープンデータ利用規約等が確認できます。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 企画部 統計課 解析活用担当
電話番号:052-972-2254 ファクス番号:052-972-4114
Eメール:a2254@somu.city.nagoya.lg.jp
総務局 企画部 統計課 解析活用担当へのお問い合わせ
