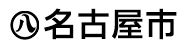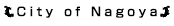名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 保険と年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険についてのよくある質問
- (現在の位置)加入・脱退・保険料についてのよくある質問(FAQ)について(国民健康保険)
加入・脱退・保険料のよくある質問(FAQ)
加入・脱退・保険料に関するよくある質問とその回答を以下に掲載しました。
令和7年度の保険料について
詳しくは、令和7年度分の国民健康保険料をご覧ください。同ページには、令和7年度保険料の具体的な計算方法や質問・回答などを掲載しています。
加入・脱退について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
- Q1-1:なぜ国民健康保険に加入しなければならないのですか。(ページ内リンク)
- Q1-2:国民健康保険への加入手続きには何が必要ですか。(ページ内リンク)
- Q1-3:名古屋市の国民健康保険に加入すると保険証は発行されますか。(ページ内リンク)
- Q1-4:資格確認書を加入手続きの日に発行してほしいです。何か必要なものはありますか。(ページ内リンク)
- Q1-5:国民健康保険をやめるときの手続きはどうすればよいですか。(ページ内リンク)
- Q1-6:国民健康保険をやめた場合の保険料の計算方法はどうなりますか。(ページ内リンク)
- Q1-7:国民健康保険の加入・脱退の手続きは、ウェブサイトや郵送で手続きできますか。(ページ内リンク)
- Q1-8:職場の健康保険に加入しましたが、資格情報のお知らせまたは資格確認書(資格情報通知書)が届きません。その間、国民健康保険の資格確認書は使えますか。(ページ内リンク)
- Q1-9:75歳になり後期高齢者医療制度に移行しますが手続きは必要ですか。(ページ内リンク)
- Q1-10:会社を退職して、職場の健康保険から脱退する場合はどうしたらよいですか。(ページ内リンク)
保険料の計算について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
- Q2-1:名古屋市の場合、国民健康保険料はどのように計算しますか。(ページ内リンク)
- Q2-2:4月・5月の保険料の暫定賦課とはどのような制度ですか。(ページ内リンク)
- Q2-3:4月・5月の暫定賦課の保険料はどのように計算していますか。(ページ内リンク)
- Q2-4:4月・5月と比べて、6月の保険料が上がったのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-5:3月に世帯員の1人が国民健康保険をやめているのに、4月と5月の金額に反映されていないのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-6:6月に国民健康保険料の納入通知書が届きました。確定申告で控除をたくさんとったはずなのに保険料が高いのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-7:確定申告した所得が国民健康保険料の所得割額に反映されていないのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-8:所得の修正申告をした場合、保険料はどうなりますか。(ページ内リンク)
- Q2-9:他市町村から名古屋市に転入してきました。前年中所得はありますが、届いた国民健康保険料の納入通知書では所得割額が0円となっているのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-10:会社を退職し、所得が減少したのに保険料が高いのはなぜですか。(ページ内リンク)
- Q2-11:年度途中で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険料はどうなりますか。(ページ内リンク)
- Q2-12:介護分保険料は、いつからかかりますか。(ページ内リンク)
- Q2-13:年度途中で65歳になる場合の介護分の保険料はどのようになりますか。(ページ内リンク)
- Q2-14:介護分保険料はどのように納付しますか。(ページ内リンク)
- Q2-15:株式の譲渡所得は、申告の有無により保険料に影響しますか。(ページ内リンク)
- Q2-16:専従者給与を受給している者の所得は、国民健康保険料の所得割額を計算する際の「基礎となる所得額」に含まれますか。(ページ内リンク)
- Q2-17:国民健康保険料の所得割額を計算する際の「基礎となる所得額」の算定において、青色申告特別控除制度(租税特別措置法25条の2)は適用されますか。(ページ内リンク)
- Q2-18:所得割額を計算する際の「所得」は、住民税における「総所得金額等」とは異なりますか。(ページ内リンク)
保険料の通知・納付について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
- Q3-1:納入通知書が届きましたが納付するにはどうしたらよいですか。(ページ内リンク)
- Q3-2:保険料の納付にはどのような方法がありますか。(ページ内リンク)
- Q3-3:口座振替で納付をしたい場合はどうしたらよいですか。(ページ内リンク)
- Q3-4:口座振替による納付ができない場合はどうしたらよいですか。(ページ内リンク)
- Q3-5:保険料の納付状況について知りたい場合はどうしたらよいですか。(ページ内リンク)
- Q3-6:保険料の納付期限はいつまでですか。(ページ内リンク)
- Q3-7:名古屋市の国民健康保険に加入していましたが、5月10日に市外に転出しました。その後6月に保険料の納付の通知が届き、6月末日が納付期限となっています。この保険料を納付する必要がありますか。(ページ内リンク)
- Q3-8:5月に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移りましたが、なぜ6月に国民健康保険料の通知が届いたのですか。(ページ内リンク)
- Q3-9:就職して勤め先の健康保険に加入したのに国民健康保険料の納入通知書が届きました。どうしてですか。(ページ内リンク)
- Q3-10:国民健康保険料納入通知書(過年度)という納入通知書が届きました。これはどのような保険料でしょうか。(ページ内リンク)
Q1-1:なぜ国民健康保険に加入しなければならないのですか。
A1-1:病気やけがをした場合、保険によって医療が受けられるように、日本では、必ずいずれかの公的医療保険に加入することが、法により義務付けられています(国民皆保険制度)。そのため、他の医療保険に加入しない(あるいは加入できない)場合は、国民健康保険に加入する必要があります。医療保険は、大きなリスクに備え、加入者それぞれが保険料を出し合い、お互いを助け合う相互扶助の制度です。制度の趣旨をご理解願います。
Q1-2:国民健康保険への加入手続きには何が必要ですか。
A1-2:下記の「必要なもの」をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお越しください。
1の手続きについては、電子申請・電子届出でも可能です。
| 番号 | こんなときには | 必要なもの |
|---|---|---|
| 1 | 職場の健康保険をやめた (被扶養者からはずれた) |
|
| 2 | 市外から転入してきた |
|
| 3 | 子どもが生まれた |
|
既に国民健康保険に加入している人と同居している場合は、既存の国民健康保険の世帯へ追加して加入します。その場合は、上記のものに加えて、次のいずれかをあわせてお持ちください。
- 加入先世帯の国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの。複数の人が国民健康保険に加入している場合は、そのうちの1枚)
- 届出人(追加して加入する人、加入先世帯で既に国民健康保険に加入している人、住民票上同じ世帯に属している人のいずれかに限ります。)の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど公的機関が発行したもの)
また、追加して加入する際に、同時に国民健康保険の世帯主が変わるときには、加入先世帯の全員の国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)をご用意ください。(全員の資格確認書等に記載されている「世帯主氏名」等を変更する必要があるためです。)
(注1)キャッシュカードは国民健康保険料の引き落とし口座の登録のために使用します。
詳しくは、キャッシュカードでの保険料の口座振替申し込みについてをご覧ください。
(注2)口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主名義の通帳など)をお持ちください。
電子申請の手続き方法については、「Q1-7:国民健康保険の加入・脱退の手続きは、ウェブサイトや郵送で手続きできますか。」をご覧ください。
その他届出に関する詳細は、国民健康保険の届出や申請に必要なものをご覧ください。また、国民健康保険の加入・脱退のページもご参照ください。
Q1-3:名古屋市の国民健康保険に加入すると保険証は発行されますか。
A1-3:国の制度改正により、令和6年12月2日(月曜日)から、従来の保険証の新規発行・再発行ができなくなりました。
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの人には、名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を発行します。
加入・脱退・保険料のよくある質問(FAQ)のトップへ戻るQ1-4:資格確認書を加入手続きの日に発行してほしいです。何か必要なものはありますか。
A1-4:資格確認書のお渡しにつきましては、通常の場合、加入手続きの後に簡易書留で郵送しますが、加入手続きの日に発行が必要な場合は、国民健康保険に加入する人またはその人と住民票上同じ世帯に属している人が加入手続きにお越しいただき、医療機関等を受診する必要がある旨をお伝えください。その際に、「Q1-2:国民健康保険への加入手続きには何が必要ですか。」の「必要なもの」とあわせて、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きのもの)をお持ちいただくことで、加入手続きの際に資格確認書をお渡しすることができます。
なお、資格情報のお知らせを加入手続きの日に発行する場合も同様です。
Q1-5:国民健康保険をやめるときの手続きはどうすればよいですか。
A1-5:下記の「必要なもの」をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお越しください。
1の手続きは郵送または電子申請・電子届出でも可能です。
2の手続きは郵送でも可能です。(引越しワンストップサービスで転出の届出をした場合は、国民健康保険の届出は不要です)
なお、同じ世帯の中で国民健康保険に引き続き加入する人が残る場合で、国民健康保険の世帯主が変わるときには、国民健康保険に残る人も含めた世帯全員の国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちのもの)もご用意ください。(全員の資格確認書等に記載されている「世帯主氏名」等を変更する必要があるためです)
郵送、及び電子申請の手続き方法については、【Q1-7「国民健康保険の加入・脱退の手続きは、ウェブサイトや郵送で手続きできますか。」】をご覧ください。
| 番号 | こんなときには | 必要なもの |
|---|---|---|
| 1 | 職場の健康保険に加入した (扶養家族になったときを含む) |
|
| 2 | 市外へ転出する |
|
| 3 | 死亡した |
|
(注)口座振替で給付金を受け取る場合は、口座番号などが確認できるもの(世帯主または葬祭執行者名義の通帳など)をお持ちください。
詳しくは、国民健康保険の届出や申請に必要なものをご覧ください。また、国民健康保険の加入・脱退のページもご参照ください。
Q1-6:国民健康保険をやめた場合の保険料の計算方法はどうなりますか。
A1-6:保険料は国民健康保険の適用を終了(資格を喪失)した月の前月までの加入月数に応じて計算します。月末に資格を喪失した場合も、喪失した月の前月までの加入月数に応じて計算します。
なお、国民健康保険をやめる手続きをいただいた後に保険料を再計算し、翌月中旬以降に保険料変更のお知らせをお送りします。保険料変更の通知が届くまでの間は、毎月の保険料のご請求は継続しますが、保険料変更の結果、お返しする保険料がある場合は、還付のお知らせを郵送します。
Q1-7:国民健康保険の加入・脱退の手続きは、ウェブサイトや郵送で手続きできますか。
A1-7:ウェブサイトによる手続きにつきましては、職場の健康保険に加入して国民健康保険をやめる場合と職場(任意継続含む)の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する場合は、名古屋市のウェブサイトより電子届出することが可能です。以下のリンク先より手続きできます。
【電子届出】国民健康保険被保険者資格取得届(職場の健康保険の脱退に伴う資格取得)
【電子届出】国民健康保険被保険者資格喪失届(職場の健康保険への加入に伴う資格喪失)
- 郵送による手続き方法:職場の健康保険に加入した場合
- 職場の健康保険の保険証、資格情報のお知らせ(資格情報通知書という名称の場合があります)または資格確認書のコピー(お持ちのもの。職場の健康保険に加入した人全員分のコピーが必要です。)
- 国民健康保険をやめる人の国民健康保険の資格確認書(お持ちの場合のみ。原本)
- 「国民健康保険をやめる届出をする」旨と連絡先を記載したメモ
- 郵送による手続き方法:名古屋市外に転出した場合
- 国民健康保険をやめる人の国民健康保険の資格確認書(お持ちの場合のみ。原本)
- 「市外転出により国民健康保険をやめる届出をする」旨と連絡先を記載したメモ
の2点をお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課まで郵送してください。
引越しワンストップサービスで転出の届出をした場合は、国民健康保険の届出は不要です。ただし、修学や病院への入院、介護施設等への入所により市外に転出する場合は名古屋市の国民健康保険の資格が継続するので、本市のお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で届出を行ってください。
Q1-8:職場の健康保険に加入しましたが、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)または資格確認書が届きません。その間、国民健康保険の資格確認書は使えますか。
A1-8:国民健康保険の資格を喪失していますので使用できません。病院などで受診する際に、保険の種類が変更したことを病院などに連絡してください。一般的には、一旦ご自身で医療費の全額を負担していただき、別途受診日時点で加入している健康保険へ保険給付分を請求していただくこととなります。資格がなくなったあとも国民健康保険の資格確認書を使用した場合、後日、その分の医療費を名古屋市へ返還していただく場合があります。
Q1-9:75歳になり後期高齢者医療制度に移行しますが手続きは必要ですか。
A1-9:75歳の誕生日から後期高齢者医療制度へ移行しますが、届出は必要ありません。マイナ保険証をお持ちでない人等は、誕生日の前日までは国民健康保険の資格確認書をお使いください。また、国民健康保険料は誕生日の前月分までかかりますが、6月の国民健康保険料の算定(本算定)の際はその分の国民健康保険料のみをあらかじめ計算のうえ通知をお送りします。
Q1-10:会社を退職して、職場の健康保険から脱退する場合はどうしたらよいですか。
A1-10:退職後に加入できる健康保険は、次の3通りあります。
- 家族の職場の健康保険の扶養家族となる→加入できる条件等、詳しくはご家族の職場にお問い合わせください。
- 退職する会社の保険を任意継続する→保険料の額、加入できる条件等、詳しくは退職する職場にお問い合わせください。
- 国民健康保険に加入する→お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で、加入の手続きが必要となります。詳しくは、国民健康保険の加入・脱退のページをご覧ください。また、保険料の額は、加入者の前年中の所得等で計算します。詳しくは、保険料の計算方法をご覧ください。
Q2-1:名古屋市の場合、国民健康保険料はどのように計算しますか。
A2-1:医療分(均等割額+所得割額)、支援金分(均等割額+所得割額)、介護分(均等割額+所得割額)のそれぞれについて10円未満の端数を切捨て合算した額が国民健康保険料になります。
| 医療分 | 診療などを受けたときに必要な医療費をまかなうための保険料 |
|---|---|
| 支援金分 | 後期高齢者医療制度の事業に要する費用を国民健康保険などの各医療保険が支払うための保険料 |
| 介護分 | 介護保険制度の事業に要する費用を国民健康保険などの各医療保険が支払うための保険料(介護分は40歳から64歳の人(介護保険第2号被保険者)にのみかかります。) |
Q2-2:4月・5月の保険料の暫定賦課とはどのような制度ですか。
A2-2:国民健康保険料は、年度ごとに前年中の世帯の所得に基づいて金額を算定しますが、年度当初には前年中の所得が把握できないため、4月と5月については暫定的に前年度の保険料の平均月額を賦課する制度です(普通徴収の場合)。
5月頃確定申告などの情報が把握できるため、普通徴収の場合は6月に、前年中の所得に基づいてその年度の保険料を確定させます(その計算を「本算定」といいます)。本算定の際は、確定した1年間の保険料額から4月・5月の暫定賦課額を差し引いて、その残りを6月から3月の10か月で割って(端数は6月分に上乗せして)お支払いいただきます(6月以降は加入者数や所得額に異動がある都度、保険料を再計算します)。
仮に暫定賦課を行わず、4月・5月の保険料がない場合は、6月から3月の10回で1年間分の保険料をお支払いいただく必要があり、1回あたりの保険料額が高くなってしまいます。暫定賦課は、4月・5月にもお支払いいただくことで年間における1回のあたりの保険料額を抑え、納付していただきやすくすることなどを目的に行っています。
Q2-3:4月・5月の暫定賦課の保険料はどのように計算していますか。
A2-3:暫定賦課保険料は前年度の2月末時点の保険料額に基づいて算定しており、3月以降に加入者数や所得額に異動があった場合でも2月末時点の保険料の平均月額となります。
また、3月から5月の間に新たに国民健康保険に加入した世帯では、新年度の保険料について暫定賦課は行われず、6月の本算定納入通知書から賦課が始まります。(なお、前年度分となる3月分は、4月に過年度分保険料として賦課されます。)
詳しくは、暫定賦課についてをご覧ください。
暫定賦課の保険料は普通徴収世帯と特別徴収世帯で以下のように計算します。
- 普通徴収世帯の場合 → 暫定賦課期間(4月・5月)における月割額は、
「前年度の年間保険料額」÷「加入月数」(100円未満切捨て)
となります。「加入月数」が12か月の場合、4月と5月の月割額は前年度の「年間保険料額」の1/12相当です。
- 特別徴収世帯の場合 → 暫定賦課期間(4月・6月・8月)における月割額は、
4月:前年度2月の月割額と同額
6月・8月:「前年度の年間保険料額」÷「加入月数」×2(100円未満切捨て)
となります。「加入月数」が12か月の場合、6月と8月の月割額は前年度の「年間保険料額」の1/6相当です。
Q2-4:4月・5月と比べて、6月の保険料が上がったのはなぜですか。
A2-4:暫定賦課の期間である4月と5月は前年度の年間保険料(前々年の所得がベース)を加入月数で割った平均月額をお支払いいただいています。その後、5月頃確定申告などの情報が把握できるため、6月に前年中の所得に基づき保険料を計算します(この計算を「本算定」といいます)。
そのため、保険料の計算の基となる所得が、4月と5月は前々年の所得、6月以降は前年の所得となり、所得が増加している場合は保険料が増加する要因となります。
また、所得が同じ場合でも、国民健康保険に加入している人数が増えることなども6月以降の保険料が増加する要因となります。
Q2-5:3月に世帯員の1人が国民健康保険をやめているのに、4月と5月の金額に反映されていないのはなぜですか。
A2-5:4月・5月の暫定賦課は、前年度の2月末時点の金額から算出しています。そのため、3月から5月に加入者数や所得額に異動が生じた場合でも、暫定賦課の保険料額に変動はありません。なお、6月の保険料算定(本算定)の際にその時の加入者数で年間保険料を計算し、4月・5月の暫定賦課額を差し引いて、その残りを6月以降の月でお支払いいただく形で保険料額を調整しています。
Q2-6:6月に国民健康保険料の納入通知書が届きました。確定申告で控除をたくさんとったはずなのに保険料が高いのはなぜですか。
A2-6:市県民税の所得割の計算では総所得金額から所得控除額を引いた金額(課税標準額)を用いて計算を行いますが、国民健康保険料の所得割の計算では総所得金額および山林所得など(退職所得は含めません)の合計額から基礎控除額のみを差し引いたものを用いて計算を行います。そのため、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除をたくさんとられていても保険料額には影響しません。
なお、確定申告などで扶養控除や障害者控除等をとられている場合、本市国民健康保険では所得割額の独自控除という独自の保険料軽減制度を行っていますので、その軽減が反映される場合があります。
詳しくは、国民健康保険料の計算方法の「独自控除制度について」をご覧ください。
Q2-7:確定申告した所得が国民健康保険料の所得割額に反映されていないのはなぜですか。
A2-7:確定申告等を期限までに申告できなかった場合や、申告期限の延長制度を利用した場合は、6月の国民健康保険料の算定(本算定)では確定申告の情報が届いておらず、所得を一旦0円として保険料の算定を行う場合があります。そのような場合は、7月以降に確定申告の内容に基づき保険料が計算され、改めて保険料の納入通知書をお送りします。
Q2-8:所得の修正申告をした場合、保険料はどうなりますか。
A2-8:国民健康保険料の納入通知書が届いた後に所得更正をした場合は、税務署等から更正後の所得情報が提供されますので、特にお手続きをしなくても、数か月後に更正後の所得情報に基づき、保険料を再計算して通知をお送りします。
数か月経っても通知が届かない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。
Q2-9:他市町村から名古屋市に転入してきました。前年中所得はありますが、届いた国民健康保険料の納入通知書では所得割額が0円となっているのはなぜですか。
A2-9:他市町村から名古屋市に転入した人は、転入時に保険料の算定の基礎である前年中の所得額が不明のため、所得を一旦0円として保険料の算定を行います。その後に前住所地へ所得照会を行いますので、所得額が判明した時点で保険料が変更される場合があります。
Q2-10:会社を退職し、所得が減少したのに保険料が高いのはなぜですか。
A2-10:保険料は、所得に対して賦課をする部分があり、これを所得割といいます。所得割は前年中の所得に基づき保険料を賦課するため、前年の途中で退職した場合でも所得割がかかることになります。
なお、特別な事情があり、国民健康保険料のお支払いが困難である人については、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
ただし、減免申請には期限が設けられておりますので、申請をご検討中の場合は、お早目にお手続きください。
また、減免につきましては、申請書等の提出後に審査を経て決定します。申請書等を提出しても減免が適用できない場合もございますので、予めご承知おきください。
保険料の減免等については、保険料を軽減する制度をご覧ください。
Q2-11:年度途中で75歳となり後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険料はどうなりますか。
A2-11:75歳の誕生日以降は後期高齢者医療制度に切り替わるため、国民健康保険料は誕生日の属する月の前月分までかかります(誕生日の属する月の分からは後期高齢者医療制度の保険料がかかります)。単身世帯の人が75歳になる場合は、75歳の誕生日の月の前月までに保険料を分けて納めていただきます。なお、4月中に75歳の誕生日を迎える単身世帯は、4月以降の国民健康保険料はかかりません。また、5月中に75歳の誕生日を迎える単身世帯は、国民健康保険料は4月分のみかかりますが、その分は前年所得が確定する6月にお支払いいただきます。
世帯の一部の人が75歳になる場合は、6月の国民健康保険料の算定(本算定)の際に75歳の誕生日の月の前月分までの保険料をあらかじめ計算し、それを翌年3月までの納期に分けています。そのため、誕生日の月に国民健康保険料は下がりませんが、後期高齢者医療制度の保険料と二重にお支払いいただくことはありません。
Q2-12:介護分保険料は、いつからかかりますか。
A2-12:国民健康保険料の中でお支払いいただく介護分保険料は、40歳から64歳の介護保険第2号被保険者が対象となり、40歳に到達する月の分からかかります。保険料の納入通知は、40歳到達月の翌月にお送りします。なお、国民健康保険被保険者が40歳に到達する前に介護分保険料を賦課することはできないため、納入通知は、納入義務が発生した時点(介護保険第2号被保険者の資格を取得した時点)以降にお送りします。
例:10月2日が満40歳の誕生日である場合(法律上は、誕生日の前日に年齢が加算されます。)
→10月1日から介護保険第2号被保険者の資格を取得し、10月分から保険料が発生します。保険料の納入通知は翌月の11月中旬にお送りし、10月分から3月分までの介護分保険料を、11月から3月までの納期に分けてお支払いいただくことになります。
Q2-13:年度途中で65歳になる場合の介護分の保険料はどのようになりますか。
A2-13:年度途中で65歳となる介護保険第2号被保険者の介護分保険料については、65歳到達月の前月までの月数で算定した額を、6月から賦課します。(4月・5月は暫定賦課のため、65歳到達有無にかかわらず前年度の平均保険料となり、6月以降の保険料で調整します。)
これにより算定された国民健康保険料(医療分、支援金分、及び月割算定後の介護分の合計)を、翌年3月までの納期に分けて納めていただきます。
65歳到達月からは、介護保険主管課より介護保険第1号被保険者の介護保険料が別途通知され、国民健康保険料とは別に納めていただくことになります。
例:10月2日が満65歳の誕生日である場合(法律上は、誕生日の前日に年齢が加算されます。)→10月1日に介護保険第2号被保険者の資格を喪失するため、国民健康保険料の中でお支払いいただく介護分保険料は9月分までとなります。6月に届く本算定の納入通知書では、4月から9月分までの介護分保険料をあらかじめ算定(10月分以降は算定から除外)し、それを翌年3月までに分割していますので、65歳に到達した10月に国民健康保険料が下がることはありません。一方、介護保険第1号被保険者としての介護保険料は10月分から発生し、別途通知が届きます。
Q2-14:介護分保険料はどのように納付しますか。
A2-14:介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の介護分保険料は、各医療保険者(市町村、健康保険組合等)に対して、医療分保険料及び支援金分保険料と合算のうえお支払いいただきます。
介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料のお支払い方法は、お住まいの区の区役所福祉課までお問い合せください。
Q2-15:株式の譲渡所得は、申告の有無により保険料に影響しますか。
A2-15:市県民税で申告不要とされている、特定口座(源泉徴収あり)に保管する上場株式等の譲渡所得及び配当所得については、申告の有無により次のようにその取り扱いが異なります。
- 申告した場合
申告した上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、国民健康保険料を計算するための所得に含めます。
なお、過去の株式等の譲渡に係る繰越損失と通算して申告した場合や、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得を損益通算して申告した場合には、損益通算後の金額になります。 - 申告しなかった場合
申告しなかった上場株式等の譲渡所得及び配当所得は、国民健康保険料を計算するための所得に含めません。
損益通算後の金額が0円以下でない場合、申告をすると保険料額が増加しますが、他の上場株式等の譲渡損失や過去の株式等譲渡に係る繰越損失との損益通算を行って税金の還付を受けるためには申告が必要となるため、どちらが有利かは一律には判断できません。
Q2-16:専従者給与を受給している者の所得は、国民健康保険料の所得割額を計算する際の「基礎となる所得額」に含まれますか。
A2-16:算入されます。そのため、専従者給与の支払者(事業主)の基礎となる所得額は、専従者給与を差し引いた後の金額となります。
一方、国民健康保険料の均等割に係る減額基準所得では、専従者給与に係る所得は含まれないため、事業主の専従者控除額は、事業主の所得に足し戻されます。減額基準所得については、保険料の所得基準による減額制度の対象となる基準所得額についてをご覧ください。
Q2-17:国民健康保険料の所得割額を計算する際の「基礎となる所得額」の算定において、青色申告特別控除制度(租税特別措置法25条の2)は適用されますか。
A2-17:基礎となる所得額の算定は、地方税法第313条第2項の規定によることとなっています。そのため、特別な規定がない限り租税特別措置法の規定が適用され、青色申告特別控除後の金額が基礎となる所得額となります。
Q2-18:所得割額を計算する際の「所得」は、住民税における「総所得金額等」とは異なりますか。
A2-18:所得割額を計算する際の「所得」は、住民税における「総所得金額等」(注)をベースとしますが、次の点で「総所得金額等」とは異なります。
- 特別控除が適用されている土地・建物等の譲渡所得は、特別控除後の金額です。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。(純損失の繰越控除は適用されます。)
- 退職所得は含めません。
(注)「総所得金額等」について
分離課税される譲渡所得や配当所得も含めたすべての所得を合計した金額です。
なお、給与の場合は「給与所得控除後の金額」(給与収入-給与所得控除額)が所得にあたり、年金の場合は「公的年金等の雑所得」(公的年金等収入額-公的年金等控除額)が所得にあたります。(非課税年金(遺族年金・障害年金)は所得に含みません。)
Q3-1:納入通知書が届きましたが納付するにはどうしたらよいですか。
A3-1:支払い方法は、納入通知書に記載されている「保険料の納付方法」の箇所をご確認ください。
Q3-2:保険料の納付にはどのような方法がありますか。
A3-2:保険料は、毎月口座振替(ゆうちょ銀行の口座の場合は自動払込)により納付していただきます。振替日は毎月末日です。(末日が金融機関の休業日の場合は、次の営業日です。)
詳しくは、保険料の納め方をご覧ください。
Q3-3:口座振替で納付をしたい場合はどうしたらよいですか。
A3-3:口座のある金融機関の窓口、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口でお申し込みください。詳しくは、保険料の納め方をご覧ください。
また、一部の金融機関では、ウェブサイトから申し込みをすることができます。
申し込み方法は、【電子申請】国民健康保険料の口座振替申し込みのサイトにあるWeb口座振替受付サイト(外部リンク) からお申し込みください。
からお申し込みください。
申し込みから口座振替の開始までに2か月程度かかります。口座振替が始まる月までは、お送りする納付書で納付してください。
Q3-4:口座振替による納付ができない場合はどうしたらよいですか。
A3-4:口座をお持ちでない等の理由により口座振替による納付ができない場合は、お住いの区の区役所保険年金課へご相談のうえ、納付書により納付してください。
納付場所等については、保険料の納め方をご覧ください。
Q3-5:保険料の納付状況について知りたい場合はどうしたらよいですか。
A3-5:所得申告等のため、1年間に納付した保険料額が必要な場合は、1月下旬から2月上旬にお送りする「国民健康保険料年間納付額のお知らせ」をご覧いただくか、区役所保険年金課へお問い合わせください。
また、各賦課年度の保険料額及び納付済額の証明が必要な場合は、国民健康保険料納付状況証明書をご覧ください。
Q3-6:保険料の納付期限はいつまでですか。
A3-6:保険料の納期限は、毎月末日です。(この日が土曜日・日曜日または祝日等のときは、次の平日になります。)
Q3-7:名古屋市の国民健康保険に加入していましたが、5月10日に市外に転出しました。その後6月に保険料の納付の通知が届き、6月末日が納付期限となっています。この保険料を納付する必要がありますか。
A3-7:この場合、転出日の前月の4月分の保険料をお支払いただくこととなりますが、4月にお送りした暫定賦課通知書では、前年中の所得が分からなかったため、暫定的に前年度の1か月当たりの平均金額を保険料額としていました。その後、前年中の所得が把握できたことから保険料額を再計算した結果、4月時点の金額と差額が生じ、その差額分の保険料額を6月にお知らせしたものとなりますので、お支払いいただく必要があります。
なお、納入通知書に7月以降も支払うべき保険料が記載されている場合は、脱退のお手続きがされていない可能性があります。
Q3-8:5月に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移りましたが、なぜ6月に国民健康保険料の通知が届いたのですか。
A3-8:この通知は4月分の国民健康保険料となります。5月に75歳の誕生日を迎える単身世帯の人につきましては、暫定賦課は行わないため4月と5月のお支払いはなく、前年中所得が確定する6月に、4月分の保険料に係る納入通知書をお送りしています。
Q3-9:就職して勤め先の健康保険に加入したのに国民健康保険料の納入通知書が届きました。どうしてですか。
A3-9:国民健康保険を脱退する手続きはお済みでしょうか。
- 国民健康保険の脱退の手続きをした場合
国民健康保険料は月割りで計算します。
年度途中で国民健康保険を脱退した場合、脱退した月の前月分までの保険料を国民健康保険料としてお支払いいただく必要があります。脱退のお手続きをいただいた後、その分の保険料を再計算(精算)し、その結果不足が生じた場合は、「国民健康保険に加入していた月の分」として納めていただくことになりますが、その通知は「国民健康保険の脱退の手続き後」にお送りしますので、他の健康保険に加入している場合でも過去の国民健康保険料の納入通知書が届くことがあります。
なお、国民健康保険料の計算対象となっている月は、届いた納入通知書の左面にある「1 被保険者氏名・保険料の計算対象となる月」欄でご確認いただくことができます。 - 国民健康保険の脱退の手続きをしていない場合
お勤め先の健康保険に加入しても国民健康保険は自動的に脱退にはなりませんので、国民健康保険をやめる手続きが必要です。手続き方法につきましては、【Q1-4「国民健康保険をやめるときの手続きはどうすればよいですか。」】をご覧ください。
Q3-10:国民健康保険料納入通知書(過年度)という納入通知書が届きました。これはどのような保険料でしょうか。
A3-10:過年度納入通知書とは「過年度相当(前年度以前)の保険料」のことで、次のような場合に発生します。
- 国民健康保険の加入手続き等の遅れにより、適用開始日(資格取得日)が前年度以前に遡及した場合
- 3月に資格を取得した場合(保険料通知の送付は翌年度4月以降となるため、3月分を過年度納入通知書としてお送りします。)
- 修正申告等により、過去の所得が増額となった場合
例:11月30日に退職し、同年12月1日から職場の健康保険を喪失したが、国民健康保険の加入手続きが翌年4月10日であった場合
→12月1日に遡って国民健康保険に加入することとなるため、12月からの加入期間の保険料の納付が必要となります。
「12月から翌年3月までの保険料」は前年度分となりますが、すでに経過した年度なので「過年度分」として賦課します。(今年度の加入期間にかかる保険料の通知とは別に通知します。)
お問い合わせ先
回答内容のさらに詳しいことについては、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問合せください。
なお、国民健康保険料の納め方については、各区の保険年金課収納担当までお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当
個別の内容については、お問い合わせ先のリンクよりお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。
電子メールアドレス: a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.