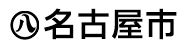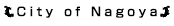名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
健康と暮らしを守る国の保険、国民健康保険と国民年金
国民健康保険は都道府県と市区町村が運営する健康保険で、私たちが病気やケガをし医療機関にかかったときに必要な保険給付などがなされます。
国民年金は、20歳から60歳までの日本に住む人が加入者となり、老齢、障害者、遺族になったときには基礎年金を受けられるシステムになっています。
国民健康保険について
どんな人が加入するのか?
会社を退職し職場の健康保険を脱退した人、市外から転入してきた人(注)、職場の健康保険の扶養に入れない人など、職場の健康保険の加入者とその扶養家族などを除いた人が、国民健康保険の加入資格者となります。
(注)すでに愛知県の国民健康保険の資格がある場合、その資格を継続します。ただし、改めて名古屋市の国民健康保険に加入する手続きが必要です。
加入手続きはどうしたらいいの?
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にて受け付けています。
退職後や高齢者の健康保険はどうなっているの?
会社などを退職後、職場の健康保険の任意継続被保険者とならない場合、退職後は国民健康保険へ加入することになります。
また国民健康保険に加入している70歳以上の人は、医療費の負担割合が2割または3割になり、高齢受給者証が交付されます(資格確認書をお持ちの人)。なお、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの人には自己負担割合が表示された資格情報のお知らせが交付されます。
資格情報のお知らせ・資格確認書と個人の医療費負担額について
国民健康保険に加入すると1人に1枚の下記のいずれかが交付されます。
- 資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの人に交付します。 - 資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない人に交付します。
個人の医療費負担は、70歳以上は2割または3割、就学児から70歳未満までは3割、未就学児は2割です。入院中の食費の負担は1食あたり510円で、市民税非課税世帯は申請により減額されます。
また、医療費が高額になった場合の高額療養費制度、医療費の支払いの減免・猶予の制度もあります。
納める保険料はいくら?
保険料を納めるのは、各世帯の世帯主です。世帯主がサラリーマンなどで国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国民健康保険加入者がいれば、その加入者の保険料は原則として世帯主が納めます。保険料は所得に応じて納めていただく所得割額と、加入者全員に等しく納めていただく均等割額を合計して、世帯ごとに計算します。なお、40歳から64歳の加入者がいる世帯については、介護保険料が上乗せされます。
保険料は、毎月、口座振替により納めていただきます。
こんなときは、手続が必要です
国民健康保険の加入者は、以下のようなケースのときもすみやかに届出が必要です。
- 職場の健康保険に加入したとき
- 引越したとき
- 死亡したとき
- 世帯や氏名の変更があったとき
など
国民健康保険の世帯主以外の加入者も届出が必要です
国民健康保険の世帯主以外の加入者も以下のケースのときは、すみやかに届出をしてください。
- 国民健康保険に加入後、職場の健康保険に加入したり職場の健康保険の扶養家族になったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 世帯が分かれたり一緒になったとき
- 40歳から64歳までの人で特定の障害者支援施設等に入所・入院したとき
など
そのほかのケースは以下のリンクをご覧ください。
国民年金とは?

国民年金は、20歳から60歳までの日本に住所のある人(外国人を含む)が国民年金に加入し、被保険者の種類に応じた保険料を国に納め基礎年金を受け取る制度です。自営業者、会社員や公務員などの人やその配偶者も対象で、学生も含みます。
国民年金からは老齢になったときは「老齢基礎年金」、障害者になったときは「障害基礎年金」、遺族になったときは「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
20歳になると基礎年金番号通知書が交付されます
20歳になったら、日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせする通知や納付書等が届きます。また、後日基礎年金番号通知書が送られます。
被保険者の種類
被保険者には「強制加入者」と「任意加入者」があります
| 種類 | 対象者 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者や学生など |
| 第2号被保険者 | 厚生年金に加入している会社員や公務員など |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満 |
任意加入者とは?
60歳以上で老齢基礎年金を受ける資格期間が不足する人(最高70歳まで)、外国に住んでいる 20歳以上65歳未満の日本人などは希望により国民年金に加入できます。
保険料はいくら?どう納めるの?
受けられる年金は

- 老齢基礎年金・・・65歳になったとき
- 障害基礎年金・・・原則65歳までに病気や事故で障害者になったとき
- 遺族基礎年金・・配偶者が死亡し、ひとり親家庭となったり、子が遺児となったとき
- 寡婦年金・・・老齢基礎年金を受ける資格をもった夫が、年金を受けずに死亡し、その妻が60歳になったとき
- 死亡一時金・・・3年以上保険料を納め、年金を受けずに死亡したとき
学生や収入が少ない、失業・災害などで保険料の納付が困難なとき
所得が少ない、災害にあったなど特別な事情がある場合には、申請により保険料の納付が全額免除(猶予)または一部(4分の3、半額、4分の1)免除されることがあります。免除(全額・一部)の決定は、前年の本人・配偶者・世帯主の所得に基づき、日本年金機構で行われます。
- 全額・一部免除(本人・世帯主・配偶者の所得)
- 納付猶予(本人と配偶者のみの所得。50歳未満)
- 学生納付特例(本人のみの所得)
産前産後期間の国民年金保険料・国民健康保険料の免除
産前産後期間の国民年金・国民健康保険の保険料が免除になりますので届出をしてください。
こんなときは、手続が必要です
- 会社や官公庁を退職・就職(転職)したとき
- 会社や官公庁に勤める配偶者(厚生年金加入者)に扶養されるようになったとき
- 会社や官公庁に勤める配偶者(厚生年金加入者)に扶養されなくなったとき
- 基礎年金番号通知書・年金手帳をなくしたとき
必要に応じて持ち物や手続場所が異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
国民健康保険・国民年金についてのお問い合わせ先
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
電話番号
:052-972-2564
ファックス番号
:052-972-4148
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.