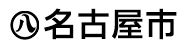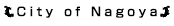名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 生活と住まい
- 生活衛生
- 飲料水の管理について
- (現在の位置)専用水道の維持管理
設置者の義務
水道法によって法定義務事項が定められています。
給水開始前の届出および検査(法第13条)
水道施設を新設、増設又は改造した場合、給水開始前に届出(第3号様式)をして下さい。また、施設が適切に施工され、水質基準に適合するかを確認するため、全項目の水質検査及び施設検査を行い、記録を検査日より5年間保存してください。
水道技術管理者の設置(法第19条)
水道の管理を適正に行うため、水道技術管理者を一人置いてください。
水道技術管理者が行うべきこと
- 水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査
- 水質検査及び施設検査
- 給水装置の構造及び材質が適合しているかどうかの検査
- 臨時及び定期の水質検査
- 健康診断
- 衛生上の措置
- 給水の緊急停止
- 給水停止命令による給水停止
水質検査の実施(法第20条)
安全な水を常時確保するため、定期及び臨時の水質検査を行い、結果を5年間保存してください。
定期の水質検査
水質を常時把握し異常の発見のために行います。1日1回、1ヶ月1回、3ヶ月1回以上行うものがあります。水源の水質変動が著しい場合、必要に応じて検査頻度を増加して下さい。水質検査については、各水道事業者(専用水道設置者)が原水や浄水の水質に関する状況に応じて、合理的な範囲で検査の回数を減じる又は省略を行うことができるとされています。従って、検査頻度を決定するにあたっては、まず、それぞれの水質基準項目について、「検査の減」又は「検査の省略」の可否を検討する必要があります。
臨時の水質検査
水源付近で消化器系感染症が流行するなど、水質基準に適合しないおそれがあるときに行うものです。
原水の水質検査
全ての水源について、水質が最も悪化していると考えられる時期を含んで少なくとも毎年1回は定期的に全項目検査を実施してください。
検査機関
水質検査は、設置者が独自に検査施設を設けるか、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に委託して水質検査を行ってください。
関係者の健康診断の実施(法第21条)
水道水の汚染を防止するため、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事する者について定期及び臨時の健康診断を行い、記録を一年間保存してください。
定期健康診断
病原体が便中に排泄される感染症について保菌者の有無を検査します。検査は、6ヶ月おきに行ってください。
臨時健康診断
健康診断対象者が便中に排泄される感染症の患者又は保菌者であることが明らかとなった場合に行うものです。
衛生上必要な措置を講ずること(法第22条)
水道の衛生確保のために消毒その他衛生上必要な措置を行ってください。
清潔の保持
取水場、貯水池、導水きょ、ポンプ等の周辺について清掃を行い、汚物等により水が汚染されないようにしてください。
塩素消毒
給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合型残留塩素の場合は0.4mg/L)以上に保持するように消毒してください。水源付近及び給水区域およびその周辺で消化器系感染症が流行している場合、遊離残留塩素を0.2mg/L結合型残留塩素の場合1.5mg/L)以上にしてください。
給水の緊急停止及び周知(法第23条)
水道施設に汚染事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときには直ちに保健所に通報するとともに、次に掲げる措置をとってください。
- 当該施設の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限の措置をとる。
- 速やかに汚染の原因を除き、当該施設の復旧を図る。
- 給水停止等の措置をとった場合は、代替水を確保する。
- 当該施設が復旧した場合は、水質検査を行って飲料水の安全を確認し、給水を開始する。
確認を受けること(法第32条)
専用水道の布設工事をしようとする場合、工事着手する前に当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて都道府県知事の確認を受けなければなりません。
給水停止命令に従うこと(法第37条)
報告の徴収及び立入検査を受けること(法第39条)
設置者が守るべき事項
- 水道法の目的の遵守(法第1条)
- 水源及び水道施設の清潔保持(法第2条)
- 水質基準の確保(法第4条)
- 施設基準の確保(法第5条)
- 施設の改善指示及び水道技術管理者の変更勧告の遵守(法第36条)
維持管理に係る提出書類
専用水道布設工事確認申請書
- 専用水道を布設工事しようとする場合、工事着手30日前までに申請して下さい。
専用水道給水開始届
- 工事完了後、給水開始前に保健所へ提出して下さい。
水質検査報告
- 水質検査(毎日検査を除く)結果を保健所へ報告して下さい。
水道技術管理者の設置・変更届
- 水道技術管理者の設置時や変更した場合、保健所へ報告して下さい。
水道事故報告書
- 水質汚染事故、断水事故が発生した場合、保健所へ提出して下さい。
記載事項変更届
- 設置者の氏名、住所等を変更した場合、保健所へ提出して下さい。
専用水道水道廃止届
- 専用水道を廃止する場合、専用水道に該当しなくなった場合、保健所へ提出して下さい。
施設の点検
帳簿書類
1 年間の管理計画
- 受水槽等の清掃・水質検査・施設点検及び健康診断についての年間の管理計画を作成しているか
2 施設の配置図等
- 主要施設(水源・浄水場・導管・受水槽・高置水槽等)の平面図及び構造図等があるか
3 施設の点検・清掃等の維持管理記録
- 施設の点検・水槽の清掃等の維持管理記録が整っているか
4 水質検査結果の記録
- 1日1回検査、1月1回検査、及び3月1回検査等を行っているか
- 記録は5年間保存しているか
5 健康診断の記録
- 健康診断(検便)を概ね6か月ごとに実施しているか
- 記録は1年間保存しているか
6 水質検査結果等の報告
- 水質検査結果等を保健所に提出しているか
水源・消毒設備
1 水源の汚染
- 水源及び水源周辺に薬剤、排水、汚水等の流入・浸透等はないか
2 水源施設の亀裂及び漏水等
- 水源施設の損傷、基礎地盤の沈下及び漏水がないか
3 水源施設の維持管理状況
- 常時清潔に保たれているか
4 消毒設備の管理
- 消毒薬は適正に注入されているか
5 消毒薬の管理
- 消毒薬使用量は記録しているか
- 補充の必要はないか
- 適正な場所に保管されているか
受水槽・高架水槽等
1 周囲からの汚染防止及び侵入防止
- 水槽の上部や周囲に油・薬剤等を置いていないか
- 人畜が侵入しないように防止柵があるか
2 ポンプ設備の状態
- ポンプは正常に稼動しているか
3 クロスコネクション
- 受水槽に給水管以外の管(汚水排水、雑排水及び消防用水等の管)が貫通や連結されていないか
4 マンホール
- マンホールの口は衛生上有効に立ち上がっているか。ふたは密閉されているか
5 水の滞留防止措置
- 流入・流出管は滞留を起こさないような位置にあるか
6 水槽内の状態
- 濁り、さび、沈殿物、藻類の発生、異物、塗装の剥離等はないか
7 吐水口空間、排水口空間
- オーバーフロー管や水抜き管は間接排水で、排水口空間はオーバーフロー管口径の2倍以上(最小でも15cm)あるか
- 吐水口空間は流入口径の2倍以上あるか
8 オーバーフロー管・通気管の防虫網
- 通気管は下向きになっているか
- オーバーフロー管・通気管に防虫網(2mmメッシュ)を設置してあるか
給水栓での水質検査(毎日検査)
1 外観(色・濁り)
- 末端での給水栓での水を透明なガラスコップに入れ、色・濁りはないか確認する
- 味・臭いに異常ないか確認する
2 残留塩素
- 残留塩素を測定し一定以上の残留塩素があるか確認する
一定以上の残留塩素とは
通常 遊離残留塩素0.1mg/L 又は結合残留塩素0.4mg/L
汚染の恐れがある場合 遊離残留塩素0.2mg/L 又は結合残留塩素1.5mg/L
地震等への対策
地震が発生した場合にも、生命の維持や生活に必要な水を安定して供給する必要があります。被害の発生を抑制し、影響を小さくするために平成20年10月1日以前に確認を受けた施設については、施設の耐震診断等を行い、耐震化計画を策定してください。また、大規模な地震に備え、大規模地震対策特別措置法に基づく専用水道に係る地震防災応急計画を作成してください。
相談窓口
専用水道維持管理についての相談は、施設のある区を担当する保健センター環境薬務課が承ります。窓口案内は、こちらからご確認ください。
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課環境衛生担当
電話番号
:052-972-2644
ファックス番号
:052-972-4153
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.