応急手当普及員が開催する講習(応急手当普及員の専用ページ)
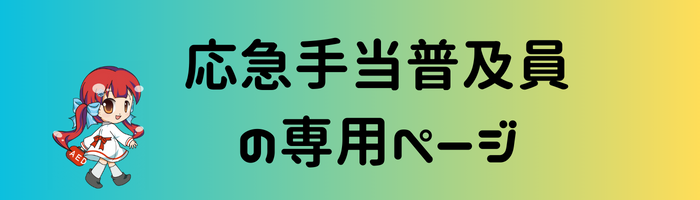
パンフレット「あなたが救える命のために 名古屋市消防局」の公開
名古屋市応急手当研修センター及び各消防署が開催する救命講習で使用しているパンフレットを更新しました。
救命講習開催前などぜひご覧ください。
このパンフレットは次の行為を禁止します
- 営利目的での使用、複製、転用、転載等あらゆる行為
- ホームページ等への無断転載
ガイドライン2020における主な変更点
令和4年10月1日から新しいガイドラインを公開
ガイドライン2020の主な変更点をまとめました。
救命講習開催時に活用してください。
新型コロナウイルス感染症流行期の対応
令和4年10月1日から救命講習で行う救急蘇生法は、「救急蘇生法の指針2020(市民用)」に沿った内容となっていますが、新型コロナウイルス感染症流行期への対応として総務省消防庁から心肺蘇生法の手順が示されました。
講習を行っていただく際は下記の内容について、受講者の皆さまにお伝えいただきますようお願いいたします。
詳細は、添付ファイルをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症流行期への対応 心肺蘇生法の具体的手順
感染予防について
講習を開催する際は、下記のとおり感染予防を行っていただきますようお願いします。
- 受講者が講習会場へ入室する前に口頭により健康状態を把握し、発熱等は救命講習等の受講を辞退していただくよう説示してください。また、手指消毒や手洗いを依頼してください。
- 講習会場は「密閉」「密集」「密接」とならないようにしてください。
- 講習用資器材は、受講者1人につき1セットを使用してください。
- 人工呼吸の実技は手順のみの指導を行い、人工呼吸の息の吹き込みを行わないようにしてください。
- 応急手当研修センター又は各消防署から貸出を受けた講習用資機材は、消毒をして返却をお願いします。なお、消毒剤などを用意することが困難な場合はご相談ください。
救命講習の開催
応急手当普及員が講習を開催する場合は、事前に実施回数分の救命講習等実施計画届の提出が必要です。
また、講習実施後速やかに修了証等交付申請書及び修了者・参加者名簿を提出してください。
応急手当普及員が開催する講習の流れ
救命講習等実施計画届
修了者・参加者名簿
修了証等交付申請書
提出先
救命講習レッスンプラン
応急手当普及員が開催することのできる各種救命講習の『レッスンプラン』です。
救命講習開催時の参考資料として自由にお使いください。
救命講習に使用する資器材の貸出しについて
応急手当普及員の方が名古屋市内で救命講習を行う場合に、応急手当研修センター又は最寄消防署で救命講習用資器材の貸出しを行っています。
併せて講習用パンフレット、修了証又は参加証もお渡しします。
一般救急講習を開催する場合は、講習用パンフレットのお渡しはできません。必要な方はホームページからダウンロードしてお使いください。
講習用資機材貸出しの予約・手続き・貸出数
応急手当研修センターにおける講習用資機材の予約期間、貸出数は下表のとおりです。
応急手当研修センターに貸出し予約の電話をしてください。
講習用資器材の予約後、救命講習等実施計画届を提出する際、裏面の訓練用資器材貸出申込書を記入してください。
| 講習種別 | 予約期間 | 1名の応急手当普及員に対しての貸出数 |
|---|---|---|
| 各種救命講習 | 3か月前から2週間前 | 10セットまで |
| 一般救急講習 | 1か月前から2週間前 | 6セットまで |
講習用資機材を貸出しできない場合
以下の何れか一つでも該当する場合は、講習用資機材の貸し出し、講習用パンフレット、修了証又は参加証の提供ができません。
- 応急手当普及員自身が所属する事業所、団体等の構成員に対する救命講習ではない場合
- 他社(者)からの依頼、委託による救命講習の場合
- 救命講習開催にあたり、講習料、参加費、謝礼など金銭等の授受がある場合
- 救命講習開催を、営利目的としている場合
- 救命講習開催場所が、名古屋市外である場合
講習用資器材一覧
- 心肺蘇生法訓練人形(成人、小児、乳児)
- AEDトレーナー
- 講習用DVD(心肺蘇生法、AED取扱い方法の動画)
- ヘッドモデル(気道確保の解説に使用する模型)
講習用資器材を借り受ける場合は、車両スペースと貸出人形の数量(嵩:かさ)をご参考の上お越しください。
貸出用人形ケースの各サイズ
講習用器材の返却要領
講習用資器材の返却は、添付資料をご確認いただきますようお願いいたします。
返却時の収納要領
講習用資機材のき損・亡失・盗難について
- 講習用資機材がき損・亡失・盗難にあったときは、講習用資機材の貸出しをした応急手当研修センター又は消防署まで直ちに連絡をしてください。
- 連絡を受けた応急手当研修センター又は消防署は、下記の「訓練用資機材[き損・亡失・盗難]届」を速やかに提出してください。
- 貸出しを受けた方の故意又は重大な過失によりき損・亡失・盗難された事が明らかな場合は、損害額に相当する金額の全部又は一部の賠償を求めることがあります。
応急手当普及員が開催する救命講習のサポート
受講者の人数に対して応急手当普及員の人数が足りない場合(応急手当普及員1名に対し受講者はおおむね10名まで)や救命講習の回数を増やすことができない場合は、応急手当研修センター又は最寄消防署の応急手当指導員を派遣し、応急手当普及員が開催する講習をサポートします。
この場合、応急手当普及員が講習の進行をしていただきます。応急手当指導員は、補助を行います。
サポート体制(講習)と出張講習の概要は下表のとおりです。
サポート講習を計画又は検討をされている場合は、事前に応急手当研修センター又は最寄消防署へご連絡ください。
| 事象 | サポート体制(講習) | 出張講習 |
|---|---|---|
| 講習申込日 | 計画又は検討時 (調整が必要なため事前に連絡をお願いします) |
講習月の3か月前の受付日 出張講習申込スケジュールによる |
| 講習用資器材の準備 | 救命講習開催側が借用・設営・返却 | 応急手当研修センター又は最寄消防署 |
| 救命講習の進行(主体) | 応急手当普及員 (応急手当指導員は補助) |
応急手当研修センター又は最寄消防署 |
| 費用 | なし | なし |
| 区域 | 名古屋市内 | 名古屋市内 |
| 提出書類 | ・救命講習等受講申込書 ・救命講習等実施計画届 ・修了証・参加者名簿 ・修了証等交付申請書 |
・救命講習等受講申込書 ・修了者・参加者名簿 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
消防局 救急部 救急救命研修所 市民普及担当
電話番号:052-853-0099 ファクス番号:052-853-1682
Eメール:00shiminfukyu@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 救急部 救急救命研修所 市民普及担当へのお問い合わせ

