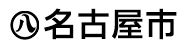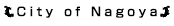名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 健康と子育て
- 子育て
- 子育てに関する手当・助成
- (現在の位置)令和6年10月の児童手当制度改正について
令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」 に基づき、令和6年10月分の児童手当から制度内容が下記のとおり変更となります。
- 支給対象となる子どもの年齢を「中学校修了まで(15歳年度末まで)」から「高校生年代(18歳年度末まで)」に延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
- 第3子以降加算のカウント対象となる子どもの年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に延長
- 支払回数を年3回から隔月の年6回に増加
| 区分 | 拡充後 (令和6年10月分以降) | 拡充前 (令和6年9月分まで) |
|---|---|---|
| 支給 対象 (注1) | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子ども | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子ども |
| 所得 制限 | 所得制限・所得上限なし | ・所得制限限度額(年収ベース、 夫婦と子ども2人の場合:960万円) 未満 → 本則給付 ・所得上限限度額(同上:1,200万円) 未満 → 特例給付 ・所得上限限度額以上は支給対象外 |
| 手当 月額 (注2) | ・3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | ・3歳未満(本則給付) 一律:15,000円 ・3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生(同上) 一律:10,000円 ・特例給付 一律:5,000円 |
| 支払 期月 | 6回(偶数月)(注3) | 3回(2月、6月、10月) |
(注1):18歳年度末までとは、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいう。
(注2):第3子以降加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする。
【例】24歳、22歳、18歳、15歳の子を養育している方の場合
→22歳を第1子、18歳を第2子、15歳を第3子とカウントする。
(注3):拡充後の初回支給は令和6年12月
児童手当制度改正のご案内


受給者について
お⽗さん・お⺟さんが共に子どもを養育している場合には、原則として、所得が⾼い方(家計の主宰者)が受給者となります。
(注)日本国籍がなくても、名古屋市に住民登録されており、在留資格があれば受給できます。
(注)家計の主宰者が公務員または市外在住の場合は手続き方法が異なります。公務員の方は職場にご確認いただき、市外在住の方はお住まいの市区町村で手続きをしてください。
(注)受給者が父母以外の方の場合、請求書と併せて「監護等申出書」の提出が必要です。(「監護等申出書」のダウンロードはこちら)
支給対象となる子どもについて
子どもが海外に居住している場合
海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件を全て満たすものとなります。
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
- 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内(注1)のものであること
(注1)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもについては、「4年以内」となります。
- 海外留学に関する申立書(申立書のダウンロードはこちら)
- 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者の翻訳が必要です)
- 従前の日本国内での居住状況の分かる書類
申請について
現在、児童手当を受給していない方
現在、児童手当を受給されていない方は、制度改正に伴い手続きが必要です。
以下に該当する方へは、8月26日(月曜日)に請求書類等を送付しました。
また、請求書類等はダウンロードすることも可能です。(申請書類のダウンロードはこちら)
令和6年度「児童手当現況届」の審査の結果、所得上限を超過したことにより受給資格を喪失した方
- 「簡易な認定請求書」を提出してください。
- 支給対象となる子どもとその兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
ご家庭の状況によって提出書類などが異なりますので、フローチャートでご確認のうえ、必要な請求書を提出してください。
提出書類確認フローチャート
過去に児童手当を受給していた方のうち、年齢超過や所得超過により受給資格を喪失した方
- 「認定請求書」を提出してください。
- 支給対象となる子どもとその兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
中学校卒業後から18 歳年度末までの子どもを養育している方
- 「認定請求書」を提出してください。
- 支給対象となる子どもとその兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を併せて提出してください。
現在、児童手当を受給している方
10月31日(木曜日)に制度改正後の支給額がわかる通知を送付しました。
通知に記載の支給対象児童数と養育状況等に相違がない場合は、手続き不要です。
以下に該当する場合など、相違がある方は、制度改正に伴い申請が必要です。
支給対象となる子どもとその兄姉等(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子ども)を含めて3人以上の子どもを養育している場合
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
- 別居している子どもがいる場合は、「額改定請求書」も併せて提出してください。
中学校修了後から18歳年度末までの子どもが反映されていない場合
- 「額改定請求書」を提出してください。
申請期間【受付は終了しました】
(注)申請期間内に受付した方については、遡って10月分から支給します。
申請書類の提出先
令和7年2月28日(金曜日)まで【受付は終了しました】
- 「児童手当拡充対応」担当(「児童手当制度改正」コールセンター)
令和7年3月3日(月曜日)以降
- お住まいの区役所民生子ども課、又は支所区民福祉課
窓口にて直接申請いただくか、ご自身で申請書類を郵送してください。
(注1)郵送の場合、区役所民生子ども課、又は支所区民福祉課に届いた日が受付日となります。
(注2)郵送に使用する封筒は、ご自身で準備をお願いいたします。
ダウンロードコーナー
申請書類
支払予定日について
- 令和6年11月18日(月曜日)までに申請を受付した方は、令和6年12月13日(金曜日)に支払いました。なお、支払予定通知は令和6年12月23日(月曜日)に発送しました。
- 令和6年12月26日(木曜日)までに申請を受付した方は、令和7年1月15日(水曜日)に支払いました。なお、支払予定通知書は1月16日(木曜日)に発送しました。
- 令和7年1月24日(金曜日)までに申請を受付した方は、令和7年2月14日(金曜日)に支払いました。なお、支払予定通知は2月13日(木曜日)に発送しました。
- 令和7年2月26日(水曜日)までに申請を受付した方は、令和7年3月14日(金曜日)に支払いました。なお、支払予定通知書は3月13日(月曜日)に発送しました。
(注1)ご提出いただいた書類に個別の確認が必要な方については、現在ご連絡をしております。確認次第、4月以降に支払います。
(注2)兄姉等による第3子以降加算の増額申請についても、上記に応じての認定となります。
(注3)令和7年2月27日(木曜日)以降に申請を受付した方は、区役所にて対応しております。区役所での審査が完了次第、4月以降に支払います。ご不明な点がありましたら、お住まいの区役所民生子ども課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
下記の電話番号及びファックス番号は、いずれも令和7年2月28日(金曜日)をもって受付を終了しました。
令和7年3月3日(月曜日)以降は、お住まいの区役所民生子ども課、又は支所区民福祉課へお問い合わせください。
名古屋市「児童手当制度改正」コールセンター【受付は終了しました】
- 電話番号:052-890-1362
- ファックス番号:052-559-1694
(受付時間 平日午前9時00分から午後5時15分まで)
審査確認及び不備対応専用の電話番号について【受付は終了しました】
- 電話番号:052‐559‐1839・050-3205-1662
よくある質問(Q&A)
Q1:「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出はどうすればいいですか?
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方は、名古屋市公式ウェブサイト(本ページ)より書類をダウンロードしていただくか、区役所民生子ども課、または支所区民福祉課の窓口にて手続きしてください。名古屋市よりお送りしたご案内(8月26日送付)には同封されておりませんのでご注意ください。
Q2:中学校修了後から18歳年度末までの子どもが就職している場合や、父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となりますか?
児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には支給対象児童となります。
Q3:18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子どもが就職していますが、第3子以降加算のカウント対象に含めることはできますか?
子どもが就職していたり、同居・別居の別に関わらず、その子どもの日常生活上の世話や定期的な連絡等を行っている、かつ経済的負担がある場合は第3子以降加算のカウント対象に含めることができます。経済的負担とは、例えば、同居であって子どもの学費や家賃・食費の少なくとも一部を親が負担している場合、別居であって親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が考えられます。
このページの作成担当
子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号
:052-972-2522
ファックス番号
:052-972-4204
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.