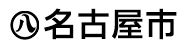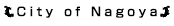名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 健康と子育て
- 健康づくりのために
- 感染症予防・予防接種
- 予防接種
- 健康被害救済制度について
- (現在の位置)B類疾病定期接種の健康被害救済制度のお知らせ
制度の概要
- 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費、障害年金等の給付)が受けられます。
- 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会(外部リンク)
 )で、因果関係を判断する審査が行われます。
)で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付の流れ

- 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて、名古屋市に請求書類を提出します。
- 名古屋市は、請求書類を受理した後「名古屋市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、愛知県を通じて国(厚生労働省)へ進達します。
- 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、愛知県を通じて名古屋市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。
- ワクチン接種時に名古屋市に住民票があった方が対象となります。
給付の種類
| 給付の種類 | 説明 | 給付額 |
|---|---|---|
| 医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給 (注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る | 保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分および入院時食事療養費標準負担額等 (注)差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外 |
| 医療手当 | 入院通院時に必要な諸経費(月単位)を支給 (注)入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る | 1か月の間に 通院3日未満 37,900円(月額) 通院3日以上 39,900円(月額) 入院8日未満 37,900円(月額) 入院8日以上 39,900円(月額) 入院と通院がある場合 39,900円(月額) |
| 障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし) (注)障害基礎年金等の額を除く | 1級 3,045,600円(年額) 2級 2,436,000円(年額) |
| 遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 | 2,664,000円(年額) 10年を限度 |
| 遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者または同一生計の遺族に支給 | 7,992,000円 |
| 葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 219,000円 |
(注)通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
(注)障害年金・遺族年金の支給開始月は、「請求があった日の属する月の翌月」になります。
(注)控除等により給付額が異なる場合があります。
【請求期限】
- 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年。
- 医療手当:当該医療を行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費・医療手当又は障害年金の支給があった場合は、死亡の時から2年。
手続きに必要な書類
- 申請書類をそろえるにあたり不明な点がございましたら、健康被害の原因となったワクチン接種時に、住民票を登録していた区の保健センター保健予防課にご相談ください。
- 申請書類提出の際は「健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB)(外部リンク)
 」にて、書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。また、記載したチェックリストは、提出書類に同封してご提出ください。
」にて、書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。また、記載したチェックリストは、提出書類に同封してご提出ください。
(1)医療費・医療手当
【請求者】
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
【必要書類】
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB)(外部リンク) | 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 |
| 2 | 医療費・医療手当請求書(PDF形式44.5KB)(外部リンク) | 【記入例】医療費・医療手当請求書(PDF形式44.7KB)(外部リンク) 【記入説明書】(PDF形式92KB)(外部リンク) 
|
| 3 | 受診証明書(PDF形式92.6KB) (外部リンク) |
|
| 4 | 領収書等の写し |
|
| 5 | 診断書(本市独自)(PDF形式19.4KB)(外部リンク) |
|
| 6 | 接種済証等の写し |
|
| 7 | 診療録等の写し (注)予防接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応であると医師が判断し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、医師が記載した「予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要(PDF形式75.5KB)(外部リンク)  」に代えることができます。 」に代えることができます。 |
|
| 8 | 高額療養費等調査・照会同意書(PDF形式25.7KB)(外部リンク) |
|
| 9 | 【必要に応じて提出】 高額療養費等の償還払額の確認書類の写し |
|
| 10 | 【必要に応じて提出】 未支給給付請求書(PDF形式26.6KB)(外部リンク)  | 【記入例】未支給給付請求書(PDF形式35.8KB)(外部リンク)
|
(2)遺族年金/遺族一時金、葬祭料
【遺族年金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した方が生計維持者の場合のその遺族(詳細は次のとおり)
- 遺族年金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹となります。
- 請求者の順位については、1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
- 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その者によって生計を維持していた子とみなします。
- 「その請求があった日の属する月の翌月」から10年間を限度として支給します。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【遺族一時金の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者又は同一生計の遺族(詳細は次のとおり)
- 遺族一時金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹となります。
- 請求者の順位については、1配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、2子、3父母、4孫、5祖父母及び兄弟姉妹の順になります。
- 配偶者以外の者(2から5までの者)については、死亡した者の死亡の当時に、その者と生計を同じくしていた者に限ります。
- 同順位の遺族が2人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【葬祭料の請求者】
予防接種を受けたことにより死亡した方の葬祭を行う方
【必要書類】
- 遺族年金/遺族一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1から10までの書類(10は必要に応じて提出)
- 遺族年金/遺族一時金のみ請求する場合:1、2、4、6から10までの書類(10は必要に応じて提出)
- 葬祭料のみ請求する場合:1、3から7まで、9の書類
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB) (外部リンク) | 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 |
| 2 | 遺族年金・遺族一時金請求書(PDF形式48.8KB) (外部リンク) | 【記入例】遺族年金・遺族一時金請求書(PDF形式54.4KB)(外部リンク) 【記入説明書】(PDF形式52.7KB)(外部リンク) 
|
| 3 | 葬祭料請求書(PDF形式37.1KB) (外部リンク) | 【記入例】葬祭料請求書(PDF形式43.3KB)(外部リンク) 【記入説明書】(PDF形式42.9KB)(外部リンク) 
|
| 4 | 死亡診断書、死体検案書の写し | - |
| 5 | 埋火葬許可証等の写し (注)遺族年金/遺族一時金のみの場合は不要 |
|
| 6 | 接種済証等の写し |
|
| 7 | 診療録等の写し |
|
| 8 | 住民票等の写し (注)葬祭料のみの場合は不要 | <遺族年金>
請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票 【死亡者と請求者が同一世帯でない場合】
|
| 9 | 戸籍謄本等の写し |
|
| 10 | その他(必要に応じて) |
|
| 11 | 遺族年金請求書(胎児用(PDF形式30.1KB))(外部リンク) |
|
| 12 | 遺族年金請求書(後順位者用(PDF形式35.9KB))(外部リンク) |
|
| 13 | 遺族年金請求書(差額一時金用(PDF形式35.4KB))(外部リンク) |
|
(3)障害年金
【請求者】
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害(3級除く)の状態にある18歳以上の方を養育する方
参考:予防接種法施行令別表第二


【必要書類】
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 健康被害救済制度チェックリスト(PDF形式113.6KB) (外部リンク) | 書類に不備・不足などが無いかご確認をお願いします。 |
| 2 | 障害年金請求書(PDF形式46.7KB)(外部リンク) | 【記入例】障害年金請求書(PDF形式47.6KB)(外部リンク) 【記入説明書】(PDF形式55.6KB)(外部リンク) 
|
| 3 | 診断書(PDF形式121KB)(外部リンク) | 【記入例】診断書(431.9KB)(外部リンク)
|
| 4 | 接種済証等の写し |
|
| 5 | 診療録等の写し |
|
(4)障害年金額変更
障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります。
【請求者】
障害年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者
【必要書類】
| 書類 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | 年金額変更請求書(PDF形式32.8KB)(外部リンク) | 【記入例】年金額変更請求書(PDF形式38.5KB)(外部リンク) 【記入説明書】(PDF形式30.1KB)(外部リンク) 
|
| 2 | 診断書(PDF形式121KB)(外部リンク) |
|
| 3 | 診療録等の写し |
|
申請にあたっての注意事項
- 提出書類の中には、発行に費用(文書費用)が生じるものがありますが、それらの費用は申請者の自己負担となります。
- 申請後、追加資料を提出していただく場合があります。
- 請求書、受診証明書、診断書以外は、すべて写しを提出してください。
- 同時に複数の申請を行う場合、重複する書類は1部で構いません。
- 全国的な申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年以上かかることがあります。
申請窓口
ワクチン接種時に住民票があった区の保健センター保健予防課
各区保健センターの窓口- 申請書類が非常に多いため、申請される際は、事前にお住まいの保健センター窓口にお電話等でご連絡いただいてからの申請をお願いします。
(注)ワクチン接種時に名古屋市外に住民票があった方は、住民票所在地の自治体へお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.