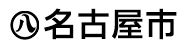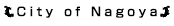名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 暮らしの情報
- 保険と年金
- 国民健康保険
- 国民健康保険についてのよくある質問
- (現在の位置)従来の保険証の新規発行・再発行の終了についてのよくある質問(FAQ)(国民健康保険)
従来の保険証の新規発行・再発行の終了に関するよくある質問(国民健康保険)(FAQ)について
国民健康保険における従来の保険証の新規発行・再発行の終了に関するよくある質問とその回答を以下に掲載しました。
制度改正の概要について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
Q1-1:従来の保険証の新規発行・再発行の終了とは何ですか。(ページ内リンク)
Q1-2:「マイナ保険証を持っている」、「マイナ保険証を持っていない」とは、どのような状態のことですか。(ページ内リンク)
従来の保険証について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
マイナ保険証について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
Q3-1:どの医療機関でも、マイナ保険証で受診できますか。(ページ内リンク)
Q3-2:マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証を登録したかどうか分かりません。どうすれば確認できますか。(ページ内リンク)
Q3-3:マイナ保険証で医療機関を受診した際に、マイナンバーカードの読み取りができませんでした。従来の保険証の新規発行終了後、マイナ保険証で受診できるか不安です。(ページ内リンク)
Q3-4:医療機関で従来の保険証の提示を求められました。マイナ保険証だけで利用できるのではないのですか。(ページ内リンク)
資格確認書・資格情報のお知らせについて
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
Q4-1:従来の保険証の有効期限が切れた後は、何を持参して医療機関を受診すればよいですか。(ページ内リンク)
Q4-2:「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を発行してもらうためには、申請は必要ですか。(ページ内リンク)
Q4-3:マイナ保険証を持っていても、申請をすれば資格確認書が交付されると聞きました。どのような人が申請をすることができるのですか。(ページ内リンク)
高齢受給者証・限度額適用認定証等について
質問項目をクリックすると、その回答へ移行します。
Q1-1:従来の保険証の新規発行・再発行の終了とは何ですか。
A1-1: 国の制度改正により、医療機関等で使用する従来の保険証が令和6年12月2日(月曜日)から新たに交付することができなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日(月曜日)以降に、例えば名古屋市の国民健康保険に加入する手続きをいただいた場合、従来の保険証の交付ができないため、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証をお使いいただき、マイナ保険証を持っていない人には従来の保険証に代わって「資格確認書」を交付することとなります。マイナ保険証もしくは資格確認書のいずれかをご使用いただくことにより、これまでどおり、一定の窓口負担で医療を受けることができます。(資格確認書についてはQ4-1からQ4-4をご覧ください。)
なお、従来の名古屋市国民健康保険の保険証は有効期限が最長で令和7年7月31日であるため、現在は使用することはできません。
Q1-2:「マイナ保険証を持っている」、「マイナ保険証を持っていない」とは、どのような状態のことですか。
A1-2:「マイナ保険証を持っている」とは、「保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを持っている」という状態のことを表します。マイナンバーカードを取得しただけでは、自動的に保険証の利用登録はされておらずマイナ保険証として利用することはできないため、マイナンバーカードの取得後、ご自身で「保険証の利用登録」を行っていただく必要があります。「保険証の利用登録」の方法については、厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用方法 」(外部リンク) をご覧ください。
をご覧ください。
一方、「マイナ保険証を持っていない」とは、「マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない」または「マイナンバーカード自体を持っていない」という状態のことを表します。
Q2-1:手元にある従来の保険証はいつまで使用できますか。
A2-1:令和6年12月1日(日曜日)時点でお手元にある有効な従来の保険証(保険証の有効期限が令和6年12月2日以降になっているものが「有効な保険証」です)は、改正法の経過措置により、有効期限まで使用することが可能です。
名古屋市国民健康保険の従来の保険証は、有効期限を最長で「令和7年7月31日」としていますので、現在は使用することができません。
Q2-2:従来の保険証は、有効期限が過ぎた後に返還する必要はありますか。
A2-2:有効期限を過ぎた従来の保険証につきましては、返還していただく必要はありません。個人情報が読み取れないよう、はさみで切るなどして破棄してください。
Q3-1:どの医療機関でも、マイナ保険証で受診できますか。
A3-1:医療機関等では、マイナ保険証に対応したシステム導入を順次進めています。厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ 」(外部リンク) にて、マイナ保険証利用に対応した医療機関・薬局のリストが掲載されていますのでご確認ください。
にて、マイナ保険証利用に対応した医療機関・薬局のリストが掲載されていますのでご確認ください。
Q3-2:マイナンバーカードは持っているが、マイナ保険証を登録したかどうか分かりません。どうすれば確認できますか。
A3-2:以下のマイナポータルから、保険証の利用登録の有無を確認することができます。ログインには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。ログイン後、「健康保険証」を押すと、マイナンバーカードの保険証利用登録の状況(「未登録」もしくは「登録済」)が表示されます。
Q3-3:マイナ保険証で医療機関を受診した際に、マイナンバーカードの読み取りができませんでした。従来の保険証の新規発行終了後、マイナ保険証で受診できるか不安です。
A3-3:通信障害や機械の故障など様々な原因が考えられますが、マイナ保険証を持っている人には、「資格情報のお知らせ」というものが交付されており、これには名古屋市の国民健康保険に加入していることが書かれています。本来の使い道は、ご自身の名古屋市の国民健康保険の資格情報を書面で簡易に把握するためですが、マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」を一緒に医療機関等の窓口で提示することにより、いつも通りの負担割合で受診することができます。なお、「資格情報のお知らせ」だけの提示では受診できません。マイナ保険証(マイナンバーカード)を一緒に提示することが必要ですのでご注意ください。(資格情報のお知らせについてはQ4-1からQ4-4をご覧ください。)
また、「資格情報のお知らせ」でなくても、マイナポータルにログイン後の健康保険の情報の画面をスマートフォンからご提示いただく方法やその情報が記載されたPDFをダウンロードしたものをご提示いただく方法でも受診が可能です。なお、これらの場合でも、マイナ保険証(マイナンバーカード)を一緒に提示することが必要です。
Q3-4:医療機関で従来の保険証の提示を求められました。マイナ保険証だけで利用できるのではないのですか。
A3-4:何らかの事情でオンライン資格確認ができなかった場合に従来の保険証の提示を求められる場合などが考えられます。ただし、従来の名古屋市国民健康保険の保険証の有効期限は最長で令和7年7月31日であるため、現在は原則として使用することはできません。
Q3-5:マイナ保険証の利用登録はしていますが、使用が難しい場合はどうすればよいですか。
A3-5:マイナ保険証を持っている人でも、要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の人などは、申請いただくことにより、資格確認書を交付することが可能です。
詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険) のページをご覧ください。(資格確認書についてはQ4-1からQ4-4をご覧ください。)
また、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、次の【Q3-6:マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか。】をご覧ください。
Q3-6:マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか。
A3-6:名古屋市の国民健康保険に加入している人につきまして、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口または郵送で申請できるほか、電子申請による申請も可能です。
窓口または郵送で申請する場合は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了について(国民健康保険) のページをご覧ください。
【電子申請は以下のリンクから】
【電子申請】国民健康保険におけるマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請(外部リンク)
(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している健康保険に申請を行う必要があります。職場の健康保険等に加入している場合は、区役所・支所では受付できませんので、加入中の健康保険にお問い合わせください。
Q4-1:従来の保険証の有効期限が切れた後は、何を持参して医療機関を受診すればよいですか。
A4-1:
- マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証をご使用ください。
なお、マイナンバーカードには氏名や住所の記載はありますが、どこの健康保険に加入しているか等の情報はカード自体には記載されていませんので、名古屋市国民健康保険の情報を書面で簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付しています。
(注) 従来の保険証(有効期限が令和7年7月31日のもの)をお持ちであった人には、「資格情報のお知らせ」を令和7年7月中旬に送付しています。 - マイナ保険証を持っていない人
従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付しています。
従来の保険証と同様に「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示していただくことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注) 従来の保険証(有効期限が令和7年7月31日のもの)をお持ちであった人には、「資格確認書」を令和7年7月中旬に送付しています。
【関連QA:Q1-2:「マイナ保険証を持っている」、「マイナ保険証を持っていない」とは、どのような状態のことですか。(ページ内リンク)】
Q4-2:「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」を発行してもらうためには、申請は必要ですか。
A4-2:マイナ保険証を持っていない人に対する「資格確認書」、マイナ保険証を持っている人に対する「資格情報のお知らせ」は、共に申請不要で発行されます。お手元の従来の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前の令和7年7月にそれぞれ送付しています。
なお、マイナ保険証を持っている人で、マイナ保険証の使用が困難な人などは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で、資格確認書の交付申請をしていただくことができます。次の【Q4-3:マイナ保険証を持っていても、申請をすれば資格確認書が交付されると聞きました。どのような人が申請をすることができるのですか。】をご覧ください。
Q4-3:マイナ保険証を持っていても、申請をすれば資格確認書が交付されると聞きました。どのような人が申請をすることができるのですか。
A4-3:下記のような人が想定されます。
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカード(電子証明書を含む)を更新中の人
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をしていても、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の人(要配慮者の人は、一度申請すれば、次回からの資格確認書の更新のときは自動的に郵送されます)
また、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、【Q3-6:マイナ保険証の利用登録を解除したい場合は、どうすればよいですか。】をご覧ください。
Q4-4:資格確認書に記載される内容は、従来の保険証と異なりますか。
A4-4:従来の保険証と同じように、資格確認書にも、氏名、性別、生年月日、保険証の記号・番号、適用開始年月日、発行している保険者の情報、有効期限などの情報が記載されるため、従来の保険証と同様にお使いいただけます。
Q5-1:従来の保険証の新規発行が終了した後、高齢受給者証はどうなりますか。
A5-1:お持ちのものにより以下のようになります。
- 資格確認書を持っている人
引き続き、高齢受給者証が交付されますので、資格確認書と併せてご使用ください。 - マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証で受診すれば、一部負担金の割合は自動的に情報連携され、高齢受給者証は不要となります。
そのため、マイナ保険証をお持ちの人には、高齢受給者証は発行されません。代わりに、資格情報のお知らせが交付されます。
一部負担金の割合は、資格情報のお知らせに記載されていますので、そちらでご確認いただくことができます。
(資格確認書・資格情報のお知らせについてはQ4-1からQ4-4をご覧ください。)
Q5-2:従来の保険証の新規発行が終了した後、限度額適用認定証等はどうなりますか。
A5-2:以下のようになります。
- 資格確認書を利用している人
オンライン資格確認を実施している医療機関等では限度額適用認定証等の提示は不要です。ただし、医療機関等の窓口で情報の提供について口頭で同意を求められる場合があります。また、提示が必要な場合は申請により限度額適用認定証等が発行されますのでご使用ください(すでにお手元にある限度額適用認定証等は有効期限まで引き続きご使用可能です。限度額適用認定証等に記載された有効期限後も引き続き限度額適用認定証等が必要な場合は、毎年7月中旬頃から8月末頃までに更新の手続きが必要となります。)。
なお、国民健康保険料に滞納がある場合は、限度額適用認定証等の交付ができないことがあり、オンライン資格確認システムにおいても限度額適用認定証等の状況を確認することができません。 - マイナ保険証を利用している人
限度額適用認定証等の提示は不要です。なお、国民健康保険料に滞納があり、限度額適用認定証等の交付ができない世帯はマイナ保険証を使った場合でも限度額適用認定証等の状況を確認することができません。
なお、入院91日目以降の長期入院の該当にはマイナ保険証利用有無に関わらず申請が必要です。
申請の際には、医療機関へ支払った領収書など、入院が90日を超えたことがわかる書類をお持ちください。
(マイナ保険証の場合、証明書等は交付されません。)
お問い合わせ先
ご不明点などについては、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問合せください。
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当
個別の内容については、各リンクよりお住まいの区の区役所保険年金課・支所区民福祉課または国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
電子メールアドレス: a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.