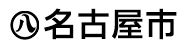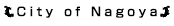名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
- トップページ
- 市政情報
- 分野別の計画・指針・調査結果
- ごみと環境保全
- ごみ関係の計画・調査結果・施策
- 埋立処分場の管理運営
- 愛岐処分場専門家会議
- (現在の位置)第28回 愛岐処分場専門家会議開催状況
開催日
令和5年1月20日(金曜日)
開催時間
午前10時から午前11時30分
開催場所
WEB会議
出席者
- 委員
座長始め7名 - 多治見市
環境文化部長始め4名 - 名古屋市
環境局施設課長始め9名 - 傍聴者
0名
1開会あいさつ
多治見市環境文化部長あいさつ、名古屋市環境局施設課長あいさつ
2委員紹介
出席委員による自己紹介
3前回のふり返り(公開)
事務局
資料A(第27回愛岐処分場専門家会議 議事要旨)について説明
4埋立状況(公開)
事務局
資料B(埋立状況、埋立量の推移)について説明
5環境モニタリング(公開)
(1)令和3年度後期から令和4年度前期の環境モニタリング結果
事務局
資料C-1(令和3年度後期から令和4年度前期 環境モニタリング結果)について説明
(2)令和5年度環境モニタリング計画の概要
事務局
資料C-2(令和5年度の環境モニタリング計画の概要)について説明
6浸出水処理施設改築事業(公開)
事務局
資料D(浸出水処理施設改築事業)について説明
7処分場の情報発信(公開)
事務局
資料E(処分場の情報発信)について説明
8質疑応答
委員
改築事業について、ウクライナ情勢や新型コロナウィルス感染症の影響による物品の納入遅延や工事の遅れはないか。
事務局
受託業者の方の感染により工事が一部止まったり、納期未定のものがあったりはするが、今のところ工期に影響はないと思っている。ただ、このような状況が重なると、工事の遅れにつながるのではないかと危惧している。
委員
工事に遅れが発生しても、安全に新しい処理施設に移行できるよう、予めプランを練っておいていただきたい。
委員
フッ素がいろいろなところから放流水や地下水に入っている。問題視する量ではないが、原因等がわかっていたら教えていただきたい。
事務局
断定はできないが、地質由来のものと考えている。
委員
過去の経緯があると思うが、脱水ケーキの溶出試験の目的を教えていただきたい。脱水ケーキに有機物等が含まれていないことを確認するためだと思うが、重金属類の含有量試験をした方がいいと思う。例えば重金属類が処理施設まできているという意味で、重金属類の含有量試験をする方がいいと思う。脱水ケーキに重金属類が含まれるということは、その前段である排出物等に含まれていたものが脱水ケーキでトラップされたということになり、徐々に含有量が増えるようであれば、排出物等に含まれる重金属類が増えたことになるため、監視目的としていいと思う。
事務局
溶出試験の目的について、過去の経緯等も踏まえ、含有量試験の追加について検討する。
委員
脱水ケーキは水に浸されているため、溶出試験をしても、おそらく何も出てこないと思う。潜在的に重金属類が発生しているという意味で含有量試験をした方がいいと思う。例えば、ある重金属類が脱水ケーキに含まれていた場合は、この処分場、処理水のところできちんとトラップできたということになり、また万が一、重金属類が徐々に増えていくことがあれば、前段の排出物等に含まれるものが徐々に増えているということになり、モニタリングの意味ではいいと思う。一度、検討いただきたい。
委員
資料B2ページの埋立量の推移について、埋立量が大きく減少している理由をお聞きしたい。
事務局
令和元年度に約5万トンあった埋立量が、令和2年度は約3万1千トン、令和3年度は2万3千トンと減少している。令和2年7月の北名古屋工場の稼働開始後、焼却物を全て資源化している。それ以前に稼働していた南陽工場から処分場に搬入されていたものが資源化されたことにより、大きく埋立量が減少した。
委員
資料C-1 17ページの脱水ケーキについて、汚泥を脱水ケーキにした後は処分しているのか。
事務局
脱水ケーキは埋立地に戻し、埋立てをしている。
委員
そういう意味では含有量を測定することも大事だと思うが、一方で、汚泥の有効利活用について研究をしている研究者もいるので、何か展開できるといいと思う。
令和5年度の環境モニタリング計画を示していただいたが、この量の項目を計測することも大事だと思うが、改めて計測地点を選んだ理由や必要性を確認し、過不足の有無も含めて確認することも大事だと思う。
排出されたごみを埋立てていると思うが、性状はどんなものか。
事務局
埋立てを開始した当初は、焼却灰以外に全体の約半分程度、不燃ごみが埋立てられていた。約15年前から焼却灰の比率が大きくなった。最近は、焼却灰が少なくなったため、焼却工場や破砕工場で処理できないブロック等が少し多く搬入されている。愛岐処分場は2回増量変更をしており、増量変更する際に性状の調査、確認を行ったが、調査する場所によりばらつきがあった。
委員
これまでの歴史もあり、どんな土が入っているのか、なかなか難しいと思うが、形状等も含め安定性の面で言うと、おそらく勾配も緩やかになっていると思うので大丈夫だと思うが、昨今は盛り土の安全性や豪雨時の安全性も問われるため、埋立形状等の目視確認をすることも大事だと思う。
委員
チェックの仕組みとして安定しており、それはとても大切なことだと思うが、他の同等施設と比較をして、今の愛岐処分場がどのようなポジションかを報告いただけると安心感が増す。他の同等施設との比較はとても重要な視点だと思う。例えば、先ほどの脱水ケーキの測定項目についても、他の同等施設でのモニタリングを参考に議論することもできる。また今後、ごみの搬入がなくなり、地形としても施設としても安定した状態となった時に、どのようなモニタリングをするのかを検討する際にも参考となる。今後のことを考えていくと、他の同等施設との比較という視点がもう少しあってもいいと感じる。
事務局
他の処分場との比較は行っていないが、今後調べていきたい。
委員
今の施設をしっかり運営していくことが大事だが、他の同等施設との比較により、この会議でいろいろな知見が披露され、専門的な知見を持った先生方の議論を経て、よりよいものにしていくといい。調査項目が減りコスト削減になってもいい。調査項目が減っても安心した施設管理ができれば十分である。処分場は物理的な施設でありながら、社会的な施設だと思うので、比較検討はとても大事だと思う。
委員
令和元年以降、埋立量が減った理由について、北名古屋工場の稼働により処理方法が変更されたためと説明があったが、発生量はあまり変わらず、処理方法の変更による減少と理解していいか。
事務局
一番大きな減少理由は処理方法の変更だが、令和元年度末以降、新型コロナの影響により、一時的に社会生活が変化し、事業系ごみ等が大きく減少したため、焼却するごみも大きく減少した。
委員
愛岐処分場の残余年数は約30年と説明があったが、愛岐処分場埋立終了後は他の二つの処分場で賄うことができるということか。
事務局
資料B2ページのとおり、現在、愛岐処分場の他、第二処分場と衣浦港3号地廃棄物最終処分場で埋立てを行っている。衣浦港3号地廃棄物最終処分場は、愛知県の広域処分場であり、当初は今年度末埋立終了予定であったが、埋立期間が10年間延長された。愛岐処分場と同じくらいの処分場であり、残余容量は40%程度と聞いている。第二処分場は、概ね15年程度埋立てを行う予定で建設された。現在7年目であり、残余容量が6割程度あるため、当初予定より長く埋立てられるのではないかと考えているが、第二処分場は海に面した処分場であり、港湾計画に組み込まれているため、現時点で明確にあと何年とは回答できないが、もともとは15年間埋立てを行う処分場として建設したため、愛岐処分場が一番長く埋立てられる処分場となっている。次の処分場確保のため、情報収集に努めている。
委員
資料B1ページの埋立実績に、破砕不燃物約千トン、市収集・自己搬入約三千トンとあるが、埋立てられているものを具体的に教えていただきたい。
事務局
平成8年に大江破砕工場が稼働する前は、粗大ごみは全て愛岐処分場に搬入されていたが、平成8年以降は大江破砕工場で粗大ごみ等を破砕し、破砕可燃物と破砕不燃物に分けて処理を行っている。ご質問いただいた破砕不燃物は、大江破砕工場で破砕された後の燃やすのに適さないものである。
委員
陶磁器類が破砕不燃物として搬入されており、金属類はリサイクルされているということか。
事務局
鉄やアルミは選別を行っているため、処分場には主にガラス等が破砕不燃物として搬入されている。破砕不燃物の一部は鳴海工場で溶融しているが、溶融しきれないものが破砕不燃物として処分場に搬入されている。市収集・自己搬入は、火災ごみ、陶器、ガラス、破砕に適さない大きなブロック等である。
委員
処分場の情報発信について、多治見市でも夏休みに親子や子供を対象とした愛岐処分場の見学会をしていただきたいと思う。
事務局
多治見市の小学生を対象とした行事について、多治見市環境課と相談し、検討する。
委員
愛岐処分場の売りになるものがあるといい。例えば、埋立てた焼却灰を再利用する技術が研究されていると思うが、現場実験等をできると処分場の残余年数を伸ばすこともできる。将来に向けて、埋立てに対する有効利活用という視点もあるといい。
事務局
通常の焼却工場では、主灰と飛灰はほぼ同量発生するが、資料B1ページの焼却灰等の内訳のとおり、埋立てを行っている主灰は飛灰に比べて少なくなっている。主灰は溶融してスラグ化する方法や、セメントの原材料として混ぜる方法など様々な資源化手法があり、現在、主灰は工場から排出される段階で資源化を行っているが、処理コストや需要の関係もあり、資源化できなかったものは処分場に埋立てられている。飛灰は、脱塩の行程を通らないと原材料として適さないが、資源化施設でもできないところが多いと聞いている。飛灰の上手な資源化方法やコストのかからない資源化方法があれば教えていただきたい。
事務局
過去に埋立てられた不燃ごみや可燃性のごみを掘り起こして溶融し、埋立量を減らすという処分場の再生事業が国内いくつかの処分場で行われているが、掘り起こしの際に発生する粉塵の対策が必要となり、また、新たな処分場を作るよりコストもかかるようである。処分場の再生事業については、これらの課題の整理が必要であるため、まだ検討段階と考えている。
委員
ごみ処理のフローチャートがあるといい。また、可能であれば、分別排出された事業系ごみや家庭ごみがどのように処理され、最終的にどのくらいの量が処分場に埋立てられるのかわかるといい。ごみ削減や分別意識の向上のため、インターネットや会議の場で情報発信をしていただくと、モチベーションアップにもつながりいいと思う。
事務局
市民の皆さんにごみ処理のフローを上手にお伝えできるよう検討する。
添付ファイル
- 資料A(第27回愛岐処分場専門家会議 議事要旨) (PDF形式, 73.28KB)

前回の議事録です。
- 資料B(埋立状況、埋立量の推移) (PDF形式, 33.91KB)

愛岐処分場の埋立状況と埋立量の推移についての資料です。
- 資料C-1(令和3年度後期から令和4年度前期 環境モニタリング結果) (PDF形式, 1.14MB)

令和3年度後期から令和4年度前期まで環境モニタリング結果についての資料です。
- 資料C-2(令和5年度の環境モニタリング計画の概要) (PDF形式, 269.11KB)

令和5年度環境モニタリング計画の概要の資料です。
- 用語解説 (PDF形式, 174.64KB)

用語解説の参考資料です。
- 資料D(浸出水処理施設改築事業) (PDF形式, 826.33KB)

浸出水処理施設改築事業の資料です。
- 資料E(処分場の情報発信) (PDF形式, 421.66KB)

情報発信についての資料です。


このページの作成担当
環境局施設部施設課事務担当
電話番号
:052-972-2372
ファックス番号
:052-972-4131
電子メールアドレス
お問合せフォーム
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.