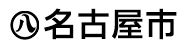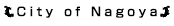名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
消防用設備等は火災から命を守るために建物に設置されています。
しかし、これらの設備の正しい使用方法を日ごろから理解していないと、
いざというとき、有効にその効果を十分に発揮できません。
そこで、消防用設備等の取扱方法や復旧方法を簡素にまとめた資料を掲載しました。
いざというとき、確実に消防用設備等が使用できるよう、ぜひご活用ください。
消火器や屋内消火栓などの消火設備の取扱方法
消火器の取扱方法
消火器は、最も身近な消防設備です。
消火剤の種類は多様で、水、強化液、泡、二酸化炭素、粉末などがあります。
最も多く用いられているのは粉末の消火器です。
※消火器の取扱方法の動画は総務省消防庁(外部リンク) をご覧ください。
をご覧ください。
※栄東まちづくりの会が作成した消火器取扱方法の動画(外部リンク) もご覧ください。
もご覧ください。
消火器の取扱方法のリーフレット
- 消火器の取扱方法 (PDF形式, 282.40KB)

消火器は様々な火災に使える身近な消火設備です。
屋内消火栓(1号消火栓)の取扱方法

屋内消火栓設備(1号)は1分間に130リットル以上の放水能力があります。
消火器より消火能力が高く、スプリンクラーより水損(放水による損害)が少ない消火設備です。
1号消火栓は従来から幅広く設置されていますが、ホースを全部引き出さないと放水できず、
通常2名以上で放水するため、日ごろの訓練が重要となります。
屋内消火栓(1号)の取扱方法のリーフレット
- 屋内消火栓(1号消火栓)の取り扱い (PDF形式, 310.04KB)

屋内消火栓(1号消火栓)には布製ホースが折り畳んで収納されています。放水時は2人で操作します。リーフレットには放水操作方法のほか、訓練等終了後の復旧方法が記載されています。
※取扱方法の動画は総務省消防庁(外部リンク) をご覧ください。
をご覧ください。
※栄東まちづくりの会が作成した屋内消火栓取扱方法の動画(外部リンク) もご覧ください。
もご覧ください。
屋内消火栓(易操作性1号・2号・広範囲型2号)の取扱方法

易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓のホースは断面が円形で、
ボックスの中に渦巻き状に収納されています。
ホースが折り畳んで収納されておらず、1人でも操作できます。
日ごろの訓練で、ホースの延長やノズル操作を確認しましょう。
易操作性1号消火栓等の取扱方法のリーフレット
- 屋内消火栓(易操作性1号・2号・広範囲型2号)の取り扱い (PDF形式, 296.09KB)

お一人の操作で放水が可能です。リーフレットには放水操作方法のほか、訓練等終了後の復旧方法が記載されています。訓練等でホース延長やノズル操作方法を確認しましょう。
※取扱方法の動画(総務省消防庁作成)は総務省消防庁(外部リンク) をご覧ください。
をご覧ください。
スプリンクラー設備の取扱方法
火災発生時に、ヘッドからの散水で自動的に消火を図る設備です。
火災を自動的に消火することができるため、たいへん有効な消火設備ですが、
消火完了確認後は、制御弁を操作し散水を止めないと、水による被害(水損)が発生します。
火災を感知し、自動的に作動するため、屋内消火栓のような放水訓練は必要ありませんが、
日ごろの訓練では、水損を防止するため、制御弁の位置や散水停止手順を確認しておきましょう。
スプリンクラー設備の取扱方法のリーフレット
- スプリンクラー設備の取り扱い (PDF形式, 376.83KB)

スプリンクラー設備は、初期消火のため、火災を自動的に感知し、散水します。消火確認後には、水損を防止するため、制御弁の操作やポンプ停止操作を行います。
その他の消火設備の取扱方法
火災を感知し、自動的に消火剤を放出し初期消火する消火設備には、駐車場等に設置されている「泡消火設備」や、
電気室に設置されている「不活性ガス消火設備」もあります。
また、屋外の駐車場等には「移動式粉末消火設備」も設置されています。
建物にこれらの設備が設置されている場合には、訓練を通じた操作要領の確認をお願いします。
泡消火設備等の取扱方法のリーフレット
- 泡消火設備の取り扱い (PDF形式, 261.10KB)

駐車場等に設置されている泡消火設備は、自動のほか手動でも泡消火薬剤を散布することができます。リーフレットには手動起動の方法や薬剤放出の停止方法(復旧方法)が記載されています。
- 不活性ガス消火設備の取り扱い (PDF形式, 248.39KB)

電気室等に設置されている不活性ガス消火設備は、自動のほか手動でも消火薬剤を放出することができます。リーフレットには手動起動の方法やガス消火剤放出についての安全対策が記載されています。
- 移動式粉末消火設備の取り扱い (PDF形式, 104.54KB)

屋外の駐車場等に設置されている移動式粉末消火設備の取扱方法です。
警報設備の取扱方法
自動火災報知設備の取扱方法
自動火災報知設備は、火災の熱や煙を自動的に感知し、音響(ベル)を鳴動させて建物内に知らせることにより、
初期消火活動や避難を促す設備です。
自動火災報知設備がないと、火災の発見が遅れ、大きな被害につながる恐れがあります。
※栄東町づくりの会が作成した自動火災報知設備の取扱方法の動画(外部リンク) もご覧ください。
もご覧ください。
自動火災報知設備の取扱方法のリーフレット
- 自動火災報知設備の取り扱い (PDF形式, 354.79KB)

自動火災報知設備が鳴動したときの対応や、鳴動したものの現場確認の結果火災でなかったときの対応が記載されています。
- 非常警報設備(放送設備)の取り扱い (PDF形式, 145.56KB)

非常警報設備(放送設備)は、多くの場合で自動火災報知設備と連動起動します。リーフレットには非常警報設備(放送設備)の手動起動方法や復旧方法が記載されています。
避難設備の取扱方法
避難器具の取扱方法
火災の際、階段が煙で充満した場合など、避難の最終手段として避難器具が設置され、
避難はしご、緩降機、救助袋などの種類があります。
※栄東町づくりの会が作成した避難梯子の取扱方法の動画(外部リンク) をご覧ください。
をご覧ください。
避難設備の取扱方法のリーフレット
- 収納式避難はしごの取り扱い (PDF形式, 400.29KB)

主に共同住宅のベランダに設置されているハッチ式の避難はしごの取扱方法と収納方法です。メーカーや設置時期により取扱方法や収納方法が異なっています。避難器具付近にある使用方法の表示を確認し、訓練等を行ってください。
- 救助袋の取り扱い (PDF形式, 545.58KB)

救助袋には斜降式と垂直式があります。訓練等を通じこれらの正しい展張方法や避難方法の習得をお願いします。


このページの作成担当
消防局 中消防署 予防課
電話番号: 052-231-0119
ファックス番号: 052-222-0119
消火器や屋内消火栓などの操作方法を習得しましょうの別ルート
- トップページ
- 暮らしの情報
- 消防・救急・火災予防
- 火災予防・規制事務に関する情報
- 消防用設備等
- (現在の位置)消火器や屋内消火栓などの操作方法を習得しましょう
サイト運営方針、所在地、連絡先など
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
Copyright(c) City of Nagoya. All rights reserved.